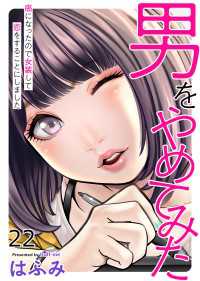内容説明
唐という国は、日本人にはなじみがあるようだ。いつまでも中国を唐といい、中国人を唐人と呼んでいた。その昔、律令や仏教や誌文を輸入し、遣唐使を派遣した記憶が残ったのだろう。たしかに唐は国際的な文化が花開いた。日本もそれにあこがれたに違いない。では、なぜあの時代に、そういう国が中国にできたのであろうか。ユーラシアの動きにかさねて、考えなおしてみよう。ダイナミックな唐という国の姿が、かならず見えてくるであろう。
目次
唐という国を考えるにあたって
1 唐王朝の成立
2 内陸アジアの遊牧民と隊商民
3 長安と外交儀礼
4 東アジア国際関係の変化
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
10
「唐の統一とは、中国の統一というよりはむしろモンゴリア南部と華北で形成される地帯の統一なのであり、それが長江流域にもおよんだとみるべき」p.24)ということを大前提として唐代の国際関係を論じる。六鎮の乱による新たな北族の南下、そこにソグド人やテュルク人がモザイク状に分布する唐。五胡十六国から安史の乱というスパンで唐を捉えており、興味深い。2019/11/23
isfahan
8
「つまり唐の統一とは、中国の統一というよりはむしろモンゴリア南部と華北で形成される地帯の統一なのであり、その力が長江流域にもおよんだとみるべき」。この視点のかっこよさ!今ある国の形、もしくは三国志などで知られる中国のイメージを根本から覆し「大陸の歴史」を描く。東アジアにおける唐のの影響の大きさを感じられる本。大化改新を引くまでもなく、唐の勃興は当時の東アジアの国々に否応なく変化を突きつけ、それが今の東アジア諸国の原型を形作る。その後、唐という母体を切り裂きローカライズされた諸国家(体制)が生まれる。2014/07/26
MUNEKAZ
5
唐の国際関係についてコンパクトにまとめた一冊。冒頭で唐皇室の系譜に触れているのが印象的。もともと中華と北方の遊牧民たちの「境界地帯」にルーツを持ち、また基盤にした唐朝だからこそユーラシアの東西にまたがる国際関係を築けたのだと思えるし、その盛期が、同じように「境界地帯」から生まれ出た安禄山によって崩壊したのも頷ける。また後半で各国からの使節に対する儀礼にも触れており、興味深い内容だった。2017/06/21
りしょう
3
唐朝の成立から滅亡目前までを簡単に記した本。比較的最新の研究成果が紹介されており、入門には最適。2018/03/13
すいか
2
唐をめぐる国際関係について、モンゴリア・ソグディアナとの政治的経済的関係、外交儀礼、国際秩序理念、「唐物」に代表される財物交換といった点から多角的にかつ平易に述べられていて、入門書として最適。特に唐から諸外国にもたらされた高級品の供給元が宮中の少府監だけではなく、地方の貧しい織工の手になる貢献の品である可能性があるという指摘は、歴史の重層性が可視化されるようで迫力があった。2019/10/08