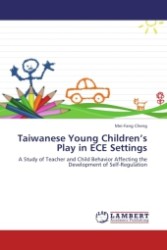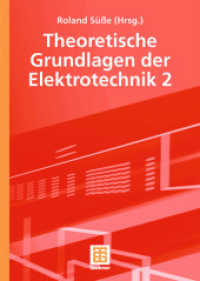出版社内容情報
軍事大国の経済破綻、改革の挫折、政治的緊張感の喪失…。アメリカ覇権の揺らぎ、ロシアの動き、米中「新冷戦」。激動の国際秩序を見通すために知りたい、歴代14帝国「崩壊」の道程を第一線の歴史学・考古学者陣が読み解く。
内容説明
軍事大国の財政破綻、改革の挫折、政治的緊張感の喪失…第一線の研究者が解く歴史上の14帝国「崩壊」の道程。
目次
8章 衰退に拍車をかけた政治的緊張感の喪失と外交の失敗―ビザンツ帝国の崩壊
9章 巨大化が遊牧帝国特有のシステムにもたらした機能不全―モンゴル帝国の崩壊
10章 領邦間のバランス喪失がきっかけの「幸福な崩壊」―神聖ローマ帝国の崩壊
11章 挫折した帝政の体制内改革と「共和制の帝国」ソ連への連続―ロシア帝国の崩壊
12章 軍事的比較優位の喪失と「ナショナリズム」による自壊―オスマン帝国の崩壊
13章 なぜ中国は少数民族の「中国化」を推し進めるのか?漢人の台頭と失われた清朝の統治精神―大清帝国の崩壊
14章 「英植民地は平和裏に独立」説は真実か―イギリス帝国の崩壊
結びにかえて 歴史上の諸帝国とその「崩壊」過程への展望
著者等紹介
鈴木董[スズキタダシ]
1947年生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。専攻はオスマン帝国史、比較史・比較文化にも深い関心を持つ。東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。