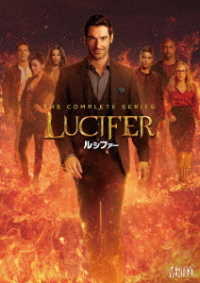出版社内容情報
古来、日本人の崇敬と畏怖の的であった不二の高嶺は、浅間さまとして国の隅々から仰ぎ祀られ、木曽御嶽は、今なお信仰登山でにぎわう。本巻ではさらに、新潟・長野・山梨・静岡・愛知各県に拡がる中部霊山と庶民信仰の関りを大きく浮彫りにする。
内容説明
本編は、中部地方における特定霊山の信仰史に関心を寄せている地元在住の研究者を中心に、その得意とする山岳信仰・修験道の諸問題について、日ごろ研鑚の一端を発表したものである。
目次
総説 富士・御嶽と中部霊山
第1篇 富士信仰の成立と甲斐の霊山
第2篇 御嶽信仰の成立と遠江の霊山
第3篇 浅間信仰の成立と信州の霊山
第4篇 戸隠・妙高の山岳信仰と修験道
第5篇 越後・佐渡の山岳信仰と修験道
著者等紹介
鈴木昭英[スズキショウエイ]
1932年新潟県長岡市に生まる。大谷大学大学院文学研究科博士課程卒。同大学助手・大阪市立博物館学芸員などを経て、現在長岡市立科学博物館館長。「松尾寺と修験道」(『大和松尾寺の歴史と文化』所収、昭和52年)『越後瞽女聞書』(講談社、昭和51年)「熊野信仰と美術」(『仏教芸術』81号)『瞽女の民間信仰」(『日本民俗学』85号)ほか論文多数
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- DVD
- 遠見には緑の春 DVD-BOX2
-
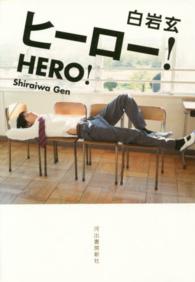
- 和書
- ヒーロー!