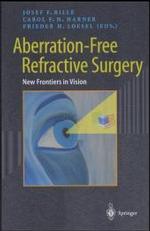内容説明
「マンホールのふた」は路面のクールジャパン!!日本各地のデザインを旅しよう。
目次
巻頭カラー特集 マンホールから見える日本の文化
1 県庁所在地を訪ねて
2 富士山と山々
3 富岡製糸場と歴史的建造物
4 いつでも見られる日本の祭りや郷土芸能
5 各地の伝統工芸・地場産業
6 地方ならではの特産物
7 地元のスポーツ自慢
8 楽しいのはデザインマンホールだけじゃない
著者等紹介
石井英俊[イシイヒデトシ]
千葉大学理学部化学科(生物化学教室)卒。2011年3月で退職するまで37年間、東京都下水道局に勤務。下水処理の水質管理と開発業務にかかわってきた。45歳から収集をはじめたマンホールの蓋の写真は4000枚を超え、現在も進行中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
星落秋風五丈原
39
「前を向いて歩く」のは「をを、前向き発言!」と礼賛されるが下を向いていると「何かにぶつかる」とやたら評判が悪い。しかし下を向かないと見られないものもある。マンホールだ。基本は人に踏まれてしまうものなので色あせているが幸い写真に映っているものはさほど色が落ちていない。静岡と山梨は断然富士山が多い。函館は五稜郭、最近「陸王」効果でたいそうな経済効果を挙げた行田市は「のぼうの城」こと忍城がデザインに採用されている。尚、本書を読んで下を向いて歩くようになっても、当局(どの?)は一切責任を持たないのでそのつもりで。2018/02/17
kiyoboo
39
仕事絡みで手に取ってみた。マンホールには、様々なデザインがあり、市の花や木や風景などが描かれいる。マニアもたくさんいてサイトも賑わっている。本書は東京都下水道局のOBが書いたものできちんと分類されているので読みやすい。地元でも旅先でも気ままに楽しめてしかもお金が掛からないのでいいと思う。最近ではゆるキャラのデザインやシールを貼ったものもあるというので、下を向いて歩こう。2015/11/02
かっぱ
35
【図書館】マンホールにみられる郷土愛。こんなのは日本だけ。その街が何を大切にしているのかが窺い知れる。京都府のマンホールは御所車の模様。市章が「京」の字をデザイン化したものとは知らなかった。ギザギザした感じが滑り止めとしても優れていそう。おっと目を見張るぐらいにデザイン的に優れたマンホールがたくさんありました。知らない街に行ったら、まず、最初にマンホールを見てしまいそう。2015/11/12
遠い日
28
マンホールから発信される町のイメージ。そこにこめられた歴史や町の特徴が、よくわかる。写真が充実しているので見応えじゅうぶん。地元のものもあった!もともと町の中のこういったものを見たり探したりするのは好きですが、さらにこれからの楽しみとなりました。2016/02/03
花林糖
18
(図書館本)デザインマンホールの紹介本。著者が折畳み自転車で全国各地をまわり、写真に撮った4000枚の中から400枚が掲載されている。花火・反物着物をデザインしたものが特に良かった。一番印象的なのは福岡県朝倉市(旧・甘木市)の消火栓の豆太鼓。マンホールの雑学も面白かった。2016/02/08
-

- 電子書籍
- 別冊マーガレット 2026年1月号
-

- 電子書籍
- 目標はひとり立ちすることです【タテヨミ…