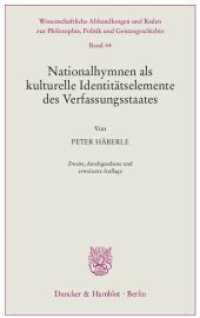内容説明
帝国海軍は軍縮条約期限後の軍備拡張を計画、その目玉は新型戦艦だった。列強各国の関心を新型戦艦から逸らすため、同時に甲型駆逐艦と一等潜水艦の建造予算が申請された。日華事変の勃発により、新型戦艦と同じ予算で水中を20ノットで潜航する新型高速潜水艦と、その潜水母艦の建造が決まる。連合艦隊は真珠湾攻撃に成功。昭和17年1月、戦艦大和は潜水母艦と新型潜水艦・伊201型と共にボルネオ島沖で初陣を迎え、英戦艦を撃沈する。そして今、米豪遮断作戦を実行するため、ポートモレスビー封鎖を目論む連合艦隊に米太平洋艦隊が立ちはだかる…。
著者等紹介
林譲治[ハヤシジョウジ]
1962年、北海道生まれ。ナイキミサイル基地訴訟で揺れ、千歳基地が隣接するという環境で育ったため、幼い頃より軍事や防衛問題に関心を抱く。戦略シミュレーションの原案などで活躍後、作家デビュー。確かな歴史観に裏打ちされた作品で人気を集める。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ikedama99
7
1巻を読んだ勢いで2巻へ。今度は「コンテナ」による標準化とその工夫、艦の設計まで変わってしまう姿をも描く。戦いは、ポートモレスビー他でのゲリラ戦が中心。戦いも含めて、作者の「思考実験」に付き合わされている感じがする。これはこれで面白い。大和、前回に続いてよく働いています。2019/12/25
ikedama99
3
コンテナの活用や、和泉のような巡洋艦、海防艦などにスポットがあたっているようにも今回は思えた。高機能な潜水艦や大和よりもそちらに注目して読んだような感じだ。続きへ。2020/06/18
zaku0087
2
大和が後半になってようやく登場した感じだが、あまり見せ場はなく、艦砲で空母撃沈というあっさりぶり。新型潜水艦はなかなかの活躍で、史実がこうだったら太平洋上にファニーウォーが訪れた可能性もあったかも。しかし、コンテナが戦略物資となり、標準規格で大量生産の潜水艦と貨物船で戦争に勝つというのは、地味といえば地味な勝ち方だが、戦後の体力温存策としては艦隊決戦よりよほどまともだ。コンテナもレーダーも陸軍発祥という皮肉も利かせていますね。2020/03/19
-
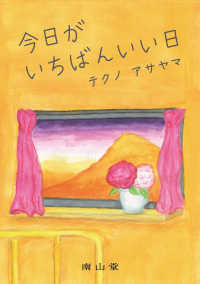
- 和書
- 今日がいちばんいい日
-
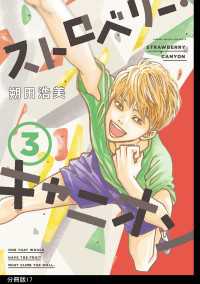
- 電子書籍
- ストロベリー・キャニオン 分冊版(17…