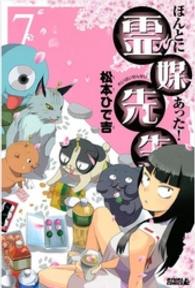目次
第1部 序論(社会的事実と社会法則の意味;コミュニティとアソシエーション;諸科学内の社会学の位置)
第2部 コミュニティの分析(コミュニティについての誤解;コミュニティの諸要素;コミュニティの構造;制度)
第3部 コミュニティの発達の主要法則(コミュニティ発達の意味;コミュニティの必滅性に関する仮定法則;コミュニティ発達の基本法則;前述法則に関連する諸問題;コミュニティ発達の第二法則―社会化とコミュニティ経済との相互関係;コミュニティ発達の第三法則―社会化と環境制御との相互関係)
著者等紹介
中久郎[ナカヒサオ]
1927年生まれ。京都大学名誉教授、愛知新城大谷大学学長。2005年歿
松本通晴[マツモトミチハル]
1930年生まれ。同志社大学文学部教授。1994年歿(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みそさざえ
2
コミュニティとアソシエーションの分類で有名な古典的名著だが、理解に時間がかかりやっと目を通した。2015/07/09
富士さん
1
第一次集団とゲマインシャフトとの違いを探るために摘読。自身を社会化する集団で、必ずしも全人格的没入を必要としない第一次集団と、相互扶助の代わりに、強制的な所属と服従を求められるゲマインシャフトと違って、コミュニティという概念は、具体的な任務を担うアソシエーションを支える合意の共同体であると読みました。コミュニティは強制によらない。自発的な意志の集合という理念型で、マッキーバー先生としては、国家のようなアソシエーションの指導者が、成員の合意を代表するとの僭称を否定するるための概念だったように見えました。2017/09/12
抹茶ケーキ
0
コミュニティはアソシエーションと異なり目的も境界ももたない。したがった国家からはあふれでる(前半)。コミュニティの発達には傾向があり、その傾向は三つの法則へと整理することができる(後半)。前半は概念整理で少し退屈。後半のグランドセオリーの方が色々考えさせられた。根底的な社会観でデュルケームと決定的に対立しているにも関わらず、要所要所でかなり接近しているのが面白かった。2016/02/15
ノーマン・ノーバディ
0
基本的にはリベラルな進歩主義ということになるんだと思う。ゲマインシャフトからゲセルシャフトへの交替を悲観的に見るテンニースに対して、マッキーバーはアソシエーションが発達することで新たな共通関心が生まれる可能性に言及するなど近代化を肯定的に捉えようとするトーンが優勢。19世紀的な文明批評と20世紀的な社会科学の中間地点という感じだが、訳者付論によると本人も古典学から社会学へと関心を移していった人らしい。時代がわかるようで面白い。2020/09/26
-
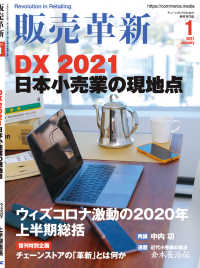
- 電子書籍
- 販売革新2021年1月号 - チェーン…
-
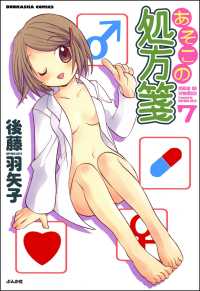
- 電子書籍
- あそこの処方箋(分冊版) 【第7話】