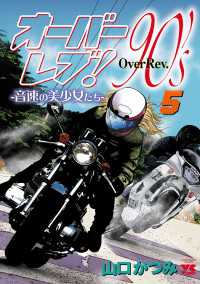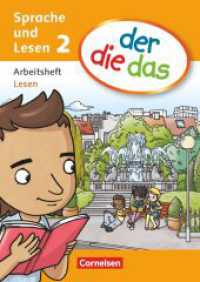内容説明
日本のマンガ界をリードし、浮き沈みの激しいマンガの世界で常にトップランナーとして、生涯走り続けた手塚治虫。その超人的な活躍の裏には、芸術と大衆文化の狭間に揺れる姿があった。マンガの神様の苦悩と格闘に焦点をあてる。
目次
第1章 豊かな環境と戦争―宝塚の時代(豊中に生まれ宝塚に;附属小学校といじめ ほか)
第2章 早熟な才能―赤本漫画の時代(マンガ家としてのスタート;「マアチャンの日記帳」連載の経緯 ほか)
第3章 ストーリー・マンガの旗手に―月刊誌の時代(上京;単行本から雑誌へ ほか)
第4章 挫折と復活―週刊誌と成人マンガ誌の時代(劇画とノイローゼ;結婚およびアニメ製作 ほか)
第5章 死と死後の評価(死をまぢかにして;死後の評価 ほか)
著者等紹介
竹内オサム[タケウチオサム]
1951年大阪市生まれ。1977年大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程(国語教育専攻)修了。現在、同志社大学社会学部メディア学科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
2
ふむ2022/07/22
marukuso
1
手塚のデヴューまでの経緯が詳しく分析されている。特に一躍有名になった『新宝島』は初版本が複数あり印刷の形式も違うらしい。本人が実年齢より2歳年上にして年齢を言っていた点はそれだけ大人っぽく見られたかったのだろうか。劇画流行期に自分の絵を変えてまで作品を創り続けたというところはアーチスト=大衆迎合的とアルチザン=職人の狭間で苦悩していたことを如実に表している。作品の量もさることながら意外な事にかの有名なトキワ荘には一年足らずしか住んでおらず、むしろ上京してから都内を頻繁に13回程引っ越していた事に驚いた。2012/09/10
わとそん
0
おもしろい2012/09/05
MAGASUS藤丸
0
早く大人になり箔をつけたかった手塚が年齢を3歳ほど上にごまかしていた為、嘘を重ねなければならなかった。それが高じサービス精神との相乗作用で、彼の回想話は、嘘や誇張・思い込みが多い。宝塚の裕福な家に生まれ、当時ではありえないディズニーやチャップリンを自宅で見れる環境に育ち、外国アニメに早くから接していた。阪大医学部かと思ったら、その下の専門学校で後阪大に吸収、医師免許を持ち、漫画作家と二足のわらじ、虫と漫画『宝島』に連載する坊ちゃん作家だった。親もマンガを悪としない環境が昭和の大漫画家手塚治虫を育んだのだ。2010/09/05
Shun Kozaki
0
手塚治虫と誕生日が一緒なだけで、変に親近感を持っている。朝日ソノラマの火の鳥がはじめての手塚治虫だった。それから、火の鳥は言うまでもなくブッダやネオ・ファウストや、ブラックジャックなど、手当たり次第に読んだが、どうにも自分の中での手塚治虫像が結べない。 結局、一番好きなのは陽だまりの樹だったりする。 奥付読んでいて気付いたが、このシリーズで柔道の祖である嘉納治五郎を担当しているのが、戦場のピアニストの主人公、ウラディシュワフ・シュピルマンの子供のクリストファー・スピルマンだ!2018/03/23