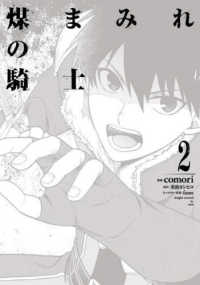出版社内容情報
【内容】
16世紀中頃のマレトロワ-ボダン論争から現代のフリードマンに至る貨幣学説を,各時代の物価問題との関連を意識しつつ簡潔に概観,経済分析における貨幣の意義を明らかにする。
【目次】
第1章 古典学派以前:ジャン・ボダンおよびシャール・カンティヨン
第1節 16世紀の著しい物価騰貴
第2節 ドゥ・マレトロアの説明
第3節 ジャン・ボダンの説明
第4節 リシャール・カンティヨンの分析
第2章 古典学派:リカードウ派と反リカードウ派
第1節 古典学派の実物分析
第2節 古典学派の貨幣的分析
第3節 反リカードウ派の伝統:ロバート・マルサス
第3章 新古典学派:レオン・ワルラスとアーヴィング・フィッシャー
第1節 新古典学派の実物分析
第2節 新古典学派の貨幣的分析
第4章 新古典学派:ケンブリッジ学派
第1節 アルフレッド・マーシャルの説明
第2節 アーサー・セシル・ピグーの公式
第3節 D.H.ロバートソンの貢献
第4節 ジョン・メイナード・ケインズの寄与
第5章 新古典学派:シカゴ学派
第1節 富の最終所有者による貨幣需要の分析
第2節 総貨幣需要関数
第3節 貨幣所得の決定モデル
第4節 理論の仕上げ:恒常的な物価と所得の概念
第5節 ミルトン・フリードマン:数量説と2分法分析
第6章 2分方的接近の妥当性?
第1節 2分法的接近の論理的価値
第2節 2分法的接近のもつ現実主義
-
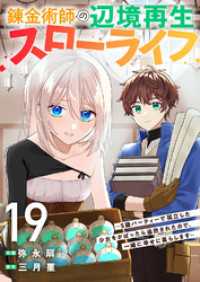
- 電子書籍
- 錬金術師の辺境再生スローライフ~S級パ…
-
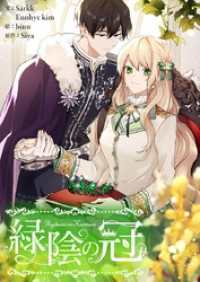
- 電子書籍
- 緑陰の冠【タテヨミ】第64話 picc…