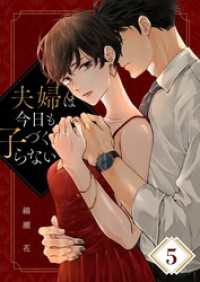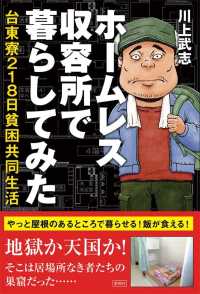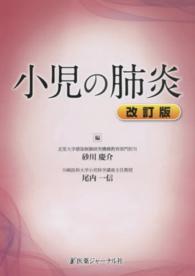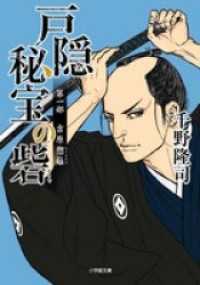出版社内容情報
アフガニスタン紛争地に従軍して両脚を失った作家が、義肢からBMIまで、障害の支援技術(アシスティブ・テクノロジー)をテーマに綴った出色のエッセイ。身体と機器の接合が自己の感覚、生活の質、障害のスティグマをいかに劇的に変えるか。機器がユーザーにもたらす希望や疑念、そして接合の代償とは──。心身の経験をさまざまな当事者の目線に沿って見つめる。
脚を失って知った、義足の賢さと面倒くささ、日常の痛み、ただれや摩擦の飼いならし方。以前、兵士だった頃は強さこそが価値とされた(「勝てないことの結果が二位であり、二位が死であるとき、弱さの入る余地はほとんどない」)。そんな著者にとってあらたな生活は、心にくすぶるエイブリズムとの格闘でもある。「障害者」という呼称も腑に落ちない著者は、機械との接合の前線を拓いている人々の話を聞きに行く。チタン‐骨結合を用いる義足の早期導入者やその開発者たち、支援機器の研究者たち、個性としての義肢の可能性を拡げるアートプロジェクト……。
その情景を曇りのない目で評価しようとする書き手の意志が、湿度を削ぎ落した語りを通して伝わってくる。義肢の歴史や、障害者の権利をめぐる闘いの足跡にも行き当たりながら、アシスティブ・テクノロジーと人間の関係の現在を描き出す。
内容説明
アフガニスタン紛争で両脚を失った作家が見つめる、障害のある身体と機械の接合による生きやすさ追求のフロンティア。語りは鉄筋なみにクール&ドライ、なのに紛れもなくヒューマンな、出色の“支援テクノロジー”考。
目次
壊れた身体の夢
ハイブリッドになる
金属の亡霊たち
インターフェーシング
取引
骨のこぎりをくれ
自由は高くつく
絶えゆく光への激しい怒り
われわれの似姿に
サイボーグがやってくる
怪物たち
金継ぎ
著者等紹介
パーカー,ハリー[パーカー,ハリー] [Parker,Harry]
作家、画家。1983年、英国ウィルトシャー生まれ。ファルマス大学、ついでユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで美術史を修めたのち、23歳で英国陸軍に入隊。2007年に小隊指揮官としてイラク戦争に従軍し、2009年には現地コミュニティとのリエゾン指揮官としてアフガニスタン紛争に従軍した。そこでIED(路肩に仕掛けられた即席爆発装置)により負傷、両脚のかなりの部分を失う。2013年に退役後、ロイヤル・ドローイングスクールで絵画の習練を再開し修士号(ファインアーツ)を取得。また、小説にも取り組み2016年にデビュー小説Anatomy of a Soldier(Faber & Faber)を発表。この作品は英国で高い評価を得て、8ヶ国語に翻訳されている。ロンドン在住
川野太郎[カワノタロウ]
1990年熊本生まれ。早稲田大学文学研究科現代文芸コース修了。翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
ズー
taku
shikada
まんぼう