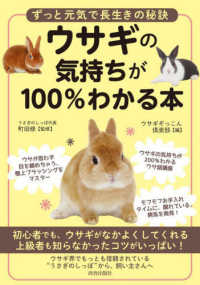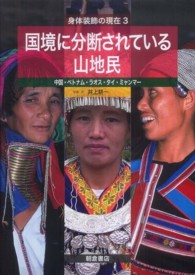出版社内容情報
アジア・太平洋戦争中、日本軍は戦地で捕らえた連合国の捕虜を一貫して虐待したというのが、今日でも欧米の共通理解となっている。映画『戦場にかける橋』や『不屈の男 アンブロークン』などにも見られるそうしたイメージは、どこまで現実を反映しているのだろうか?
1941年12月の真珠湾攻撃とマレー半島上陸から5カ月のうちに、日本軍は14万人以上の連合軍兵士と13万人の民間人を捕虜にし、満洲からジャワまで各地に急造した700カ所以上の収容所に収容した。混乱のなかで米兵捕虜の約4割が命を落とし、収容所で死亡したオーストラリア兵捕虜の数は、戦場の戦死者よりも多かった。
日本研究者である著者は、明治維新以降の歴史を精緻に踏まえつつ、シンガポール、フィリピン、朝鮮、福岡など特徴的な収容所を選んで捕虜たちが残した記録や証言にあたり、かれらの置かれた状況を立体的に再現する。日本側と捕虜側双方の人種偏見、朝鮮や台湾出身の軍属、アジア人や女性捕虜への目配りも怠りない。綿密な調査により、捕虜に対する過酷な扱いのほとんどは、日本側の計画の欠如、貧弱な訓練、官僚主義に起因しており、統一的な〈虐待〉方針が存在したわけではないことを裏付ける。また、収容所での虐待よりも、友軍による爆撃や移送中の魚雷攻撃で死亡する捕虜の方が多かった。
「何を記憶し、何を忘れ去るかは社会に委ねられているのである」(序章より)。戦争を総体として捉え、今日の捕虜や軍事法廷をめぐる問題を考えるうえでも欠かせない歴史研究。
内容説明
アジア・太平洋戦争中、日本軍の捕虜となった数十万の連合軍兵士と一般市民は、いかなる状況に直面したのか?日本をはじめ各国での文献調査と生存者への聞き取りをもとに、偏見を排し実態に迫る歴史研究。
目次
広く知られる奇妙な歴史
近代化の旗手から無法国家へ
シンガポール―ひっくり返った世界
フィリピン―地獄のコモンウェルス
言葉の戦争
朝鮮―模範収容所の生と死
銃後の捕虜収容所
終わりと始まり
不当な手続き
歴史の虜囚―戦後のジュネーブ条約の再交渉
二度と、再び繰り返さない
著者等紹介
コブナー,サラ[コブナー,サラ] [Kovner,Sarah]
コロンビア大学サルツマン戦争と平和研究所上席研究員(日本研究)。イェール大学国際安全保障研究所フェロー、フロリダ大学准教授(歴史学)も務める。コロンビア大学で博士号取得。京都大学、東京大学でも研究を行なう。初の著書Occupying Power:Sex Workers and Servicemen in Postwar Japan(Stanford University Press,2012)は、米国大学・研究図書館協会(ACRL)書評誌Choiceが選ぶ「Outstanding Academic Title」(傑出した学術書籍)に選ばれている
白川貴子[シラカワタカコ]
獨協大学外国語学部講師
内海愛子[ウツミアイコ]
1941年生まれ。早稲田大学大学院文学部社会学専攻修了。恵泉女学園大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nnpusnsn1945
おかむら
ケイトKATE
田中峰和
takao
-
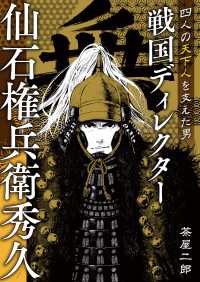
- 電子書籍
- 戦国ディレクター 仙石権兵衛秀久 - …