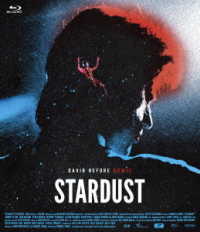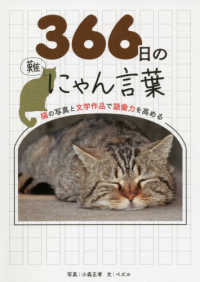内容説明
寺田寅彦は「二つの文化」、自然科学と文学という二つの領域において輝かしい業績を遺した。科学にあっては、ゆらぎやアポトーシスなど、複雑系の科学への流れを想定し、映画や連句においてはモンタージュ論によって芸術理論の革新を計った。本書は、科学における多くの先見の明、戦争や地震災害にたいする対応などから、多面的な人間=寅彦の全体像を初めて明らかにし、その遺産を近・現代科学史に位置づけた刺戟的な労作である。
目次
第1章 「二十世紀の豫言」と現代
第2章 寺田寅彦が提唱した新しい科学
第3章 技術と戦争を巡って
第4章 科学・科学者・科学教育
第5章 自然災害の科学
第6章 科学と芸術
第7章 寅彦と宇吉郎、そして現代
著者等紹介
池内了[イケウチサトル]
1944年兵庫県生まれ。総合研究大学院大学名誉教授。名古屋大学名誉教授。宇宙物理学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nagata
3
良質な科学随筆。時折寺田氏の言葉を借りながら、科学の本質から課題までを掘り下げてくれている。科学の限界というか醜悪な部分は筆者が改めて言明するまでもないところが多いが、「純粋な科学」、子どもが何?なんで?と無垢な目を向けてじっと考えてみるという原点のようなものに立ち返ることは果たしてできるのだろうか。個人的には、科学と芸術との相似のところが一番面白かった。2023/03/13
ベルナデッタ
2
寺田寅彦が残した言葉を追いながら、現代を生きる私たちと科学の関係性について解説している。この本自体が既に書かれてから18年経っているが、著者の池内氏が指摘する科学と人類延いては地球の問題の核になる部分は今と然程変わっていないため、読んでも時代遅れ感はない。特に最終章で論じられている「産官学」の連携が基礎研究の存在を脅かしている問題は改めて今も深刻だと感じ、昨今の大学の在り方についてまた考えさせられる。2023/01/22