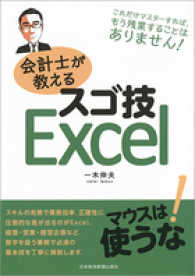出版社内容情報
憲法改正、領土問題、歴史認識問題はなぜ、こんなにも軋轢を招くのか。アメリカで教える気鋭の社会学者が比較文化の視点から、日本の「敗戦の文化」を考察する。
私たちが家族、学校、メディアをとおして触れる戦時の物語は多様だ――戦場で英雄だった祖父、加害の体験を話さずに逝った父、トラウマを解消できない被害者たち。それらの記憶は、史実に照らして見直されることなく共存し、家族内では、調和が最優先される語りが主観的に選び取られる。
高校の歴史教科書・歴史漫画の分析からは、なぜ若い世代が自国に自信をもてないか、その理由が見えてくる。
そしてメディアは、記憶に政治色をつけながら、それぞれ違う物語を映し出す。
戦後70年を過ぎた今、不透明な過去に光を当て、問題の核心に迫る。
内容説明
憲法改正、領土問題、歴史認識問題はなぜ、こんなにも軋轢を招くのか。アメリカで教える気鋭の社会学者が比較文化の視点から、日本の「敗戦の文化」を考察する。私たちが家族、学校、メディアをとおして触れる戦時の物語は多様だ―戦場で英雄だった祖父、加害の体験を話さずに逝った父、トラウマを解消できない被害者たち。それらの記憶は、史実に照らして見直されることなく共存し、家族内では、調和が最優先される語りが主観的に選びとられる。高校の歴史教科書・歴史漫画の分析からは、なぜ若い世代が自国に自信をもてないか、その理由が見えてくる。そしてメディアは、記憶に政治色をつけながら、それぞれ違う物語を映し出す。戦後70年を過ぎた今、不透明な過去に光を当て、問題の核心に迫る。
目次
第1章 敗戦の傷跡と文化的記憶(文化的トラウマ、記憶、国民アイデンティティ;戦争の記憶をめぐる三つの道徳観とその語り ほか)
第2章 個人史と家族史を修復する記憶(戦中世代の証言;語らない親との対話―溝を埋め、傷を癒す ほか)
第3章 敗北感の共有とその位置づけ―メディアのなかの英雄、被害者、加害者の物語(政治パフォーマンスとしての追悼;追悼の季節の文化メディア ほか)
第4章 戦争と平和の教育―子供にどう第二次世界大戦を教えるか(上からの歴史―教科書のなかの戦争と平和;下から見た歴史―「学習漫画」のなかの戦争と平和 ほか)
第5章 敗戦からの回復とは何か―他国との比較から(敗戦の文化を乗り越える―道義的回復に向けた三つの展望;和解のグローバル・モデルはあるのか ほか)
著者等紹介
橋本明子[ハシモトアキコ]
1952年東京生まれ。幼少期・青年期をロンドン、東京、ハンブルクで過ごす。1975年、ロンドン大学(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)社会学部卒業。東京のソニー本社勤務を経て渡米。1984年、イェール大学大学院社会学部博士号取得。東京の国連大学本部勤務を経てふたたび渡米。1989年以降、ピッツバーグ大学社会学部で教鞭をとる。現在、米国ポートランド州立大学客員教授、イェール大学文化社会学研究所客員研究員を兼任
山岡由美[ヤマオカユミ]
津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。出版社勤務を経て翻訳業に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
molysk
おさむ
きいち
おかむら
-
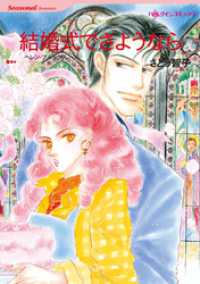
- 電子書籍
- 結婚式でさようなら【分冊】 12巻 ハ…
-

- 電子書籍
- インパクト 26