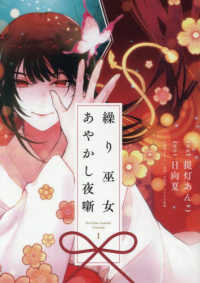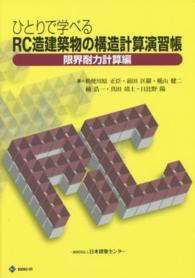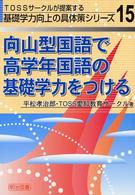内容説明
真実の歴史を物語ることはいかにして可能か。フィクションと真実のあいだにある、偽って真実であると見せかけている歴史的素材を丹念に解きほぐす全6編。
目次
1‐1 描写と引用
1‐2 パリ、一六四七年―作り話と歴史についてのある対話
2‐1 寛容と交易―アウエルバッハ、ヴォルテールを読む
2‐2 冷厳な真実―歴史家たちへのスタンダールの挑戦
3‐1 細部、大写し、ミクロ分析―ジークフリート・クラカウアーのある本に寄せて
3‐2 ミクロストリア―彼女についてわたしの知っている二、三のこと
著者等紹介
ギンズブルグ,カルロ[ギンズブルグ,カルロ][Ginzburg,Carlo]
歴史家。1939年イタリアのトリーノに生まれる。ピサ高等師範学校専修課程修了。長らくボローニャ大学で近世史講座の教授職にあったのち、1988‐2006年カリフォルニア大学ロスアンジェルス校で教える。現在はピサ高等師範学校教授
上村忠男[ウエムラタダオ]
1941年兵庫県尼崎市に生まれる。東京大学大学院社会学研究科(国際関係論)修士課程修了。東京外国語大学名誉教授。学問論・思想史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
10
本書は文芸批評のようにも読めます。 文献にあたる学問ということで、本質的な違いはないのだと思います。 歴史は考古学などの物的証拠も重要ではありますが、文芸批評に考古学(考現学・社会学)の知見を取り入れても問題ないように、全ては繋がって、今現在とは別の現実を織りなしていく。 2022/11/09
ラウリスタ~
8
ギンズブルグというのはフランスの歌手ではない、イタリアの歴史家だ。歴史を語るという行為を真実を語らなければならないことであって、明らかに小説とは異なるはずのものである。しかしながら、バルザックやスタンダールの小説は同時に重要な歴史的資料にもなる。その時代の空気感すべてを詰め込むような小説や、幹ではなく葉の一枚一枚の断片に注目することで普遍的な理解へと到るプルースト・ウルフ的歴史など。フィクションと歴史との間に関する論文集。アウエルバッハの『ミメーシス』が重要な典拠となる。2015/03/29
roughfractus02
7
貝殻の化石が山肌に埋もれているのを見て、この貝は海にいるから昔ここは海だったのだろう、と推論するのが遡行推理である。この推論が発見の論理とされるのは「この貝は海にいる」という少量の知識から想像力によって「昔海だったのだろう」と飛躍的な仮説を作るからだ。本書でこの推論を「糸」に、貝殻のような資料断片を「痕跡」に喩えた著者は、歴史編纂をする歴史家が資料を事実とフィクションに分けるのに対し、アウエルバッハ『ミメーシス』の文学伝統も資料として扱い、事実が伝達不能な歴史の生き生きした伝え方(喩法や話法)を発見する。2020/04/15
takao
2
ふむ2024/11/27
gachin
2
進化の研究をしてることもあり、歴史を叙述するとはどういう作業なのかを知りたくて読んだ。論文集の和訳。上品で誠実語り口で、中立的で冷静な文体なので、水のようにスラスラ読めてしまうんだけど、逆に引っかかりがなさすぎて何を伝えてる文章なのかが判らないのが多かった。最後の一遍だけは自分にとって学ぶところが多く、読むのにすごく時間がかかったし充実感を感じた。歴史の手掛かり自体もそれを読み取る学者も、ストーリーを作り過ぎるから注意が必要だけど、それもまた意義が無い訳ではない。著者の他の本も読んでみたいと思った。2019/08/18
-
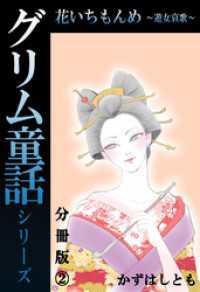
- 電子書籍
- グリム童話シリーズ 花いちもんめ~遊女…
-

- 電子書籍
- ワスレモノ (1)