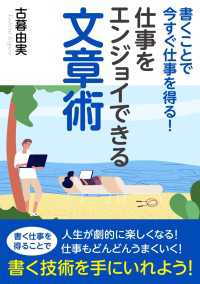出版社内容情報
本書は3.11に直面し,厚労副大臣として対応に当った著者が,事実,経緯をできる限り正確に記した記録で,ネットではなく活字に留め広く公開するため急遽刊行することとなった。
とくに食品などを中心とする放射性物質に対する対応・対策・指針・規制は,その当否が後世に問われる深刻な問題なので,多くの国民が読むことのできる形式にして,残しておくことがきわめて重要である。そこで、本書は合理的で、理性的であることを第一に、3.11当時の責任者・当事者が客観的に事実に基づいて放射線物質の影響や規制について語られている。
大塚耕平
1959年生まれ。早稲田大学卒業後、2000年まで日本銀行に勤務。2001年から参議院議員。2009年 内閣府副大臣(金融・郵政改革・経済財政・地域主権改革等を担当)2011年厚生労働副大臣。著書に「小泉改革とは何だったのか」(共著、日本評論者2006)「検証格差拡大社会」(共著、日本経済新聞社2006)など。
内容説明
厚労副大臣として3.11被災者の救助・救援、医療支援、さらに食品の放射性物質の暫定規制、放射線の健康影響への対応などに携わった当事者の記録。これから長い間、わが国は放射性物質と向き合っていかざるをえない。放射性物質規制の当否の判断は後世に委ねられるが、本書は、後世の検証に資するためにも、暫定規制導入の経緯、その後の動向を記録したものである。
目次
1章 東日本大震災と福島第一原発事故(厚労省副大臣室;災害救助法担当;1号機爆発で脳裏をよぎった放射能汚染;計画停電への対応)
2章 暫定規制と出荷制限(暫定規制導入;米国の五〇マイル規制(三月一七日未明)
ICRP委員長公開書簡(三月二一日)
食品検査と出荷制限)
3章 科学の信頼と日本の未来(リスクコミュニケーション;ハイケアの「〇.〇四%」;最低被曝量の「五.二mSv」;内部被曝量の「五三一Bq」;ラジウムの「三.三五μSv」;NIMBYシンドローム;日本の未来)
4章 暫定規制の考え方と新規制(原子力安全委員会の平成一〇年報告書;四月一日の資料;低線量被曝の影響;暫定規制見直し(四月からの新規制))
5章 放射性物質との対峙(放射性物質とは何か;原子力の発見と原爆実験;環境放射線被曝;原子力政策)
著者等紹介
大塚耕平[オオツカコウヘイ]
1959年生まれ。1983年、早稲田大学卒業。1983~2000年、日本銀行に勤務。日銀在職中に早稲田大学大学院博士課程修了(学術博士、専門はマクロ経済学)。2001年から参議院議員、現在2期目。2009~2010年、内閣府副大臣、2011年、厚生労働副大臣。現在、中央大学大学院と早稲田大学の客員教授を兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。