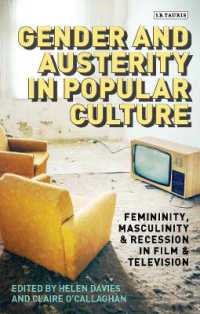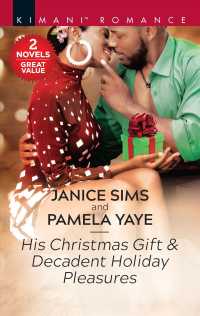内容説明
本書では、実際の自然現象の抽象化と数理的単純化、モデル化のプロセスとその意味を見ていく。物理法則や公式がなぜ必要で、いかに使われ、どのように役立つかがわかるだろう。「物理の役割は、森羅万象を相手にして自然界の真理、つまりものごとの成り立ち、仕組みとはたらきを明らかにすることだ。このとき、論理性、実証性と柔軟な方法論が武器となる。」パリティ誌の好評連載を単行本化。
目次
どれがいちばん偉い?―クーロンの法則、フックの法則、摩擦の法則
カーリングとニュートリノ―力学の質点のモデルと実際の物体
雨粒でケガをしないのはなぜ?―摩擦の法則と粘性抵抗
風船の吹きはじめに力がいるのはなぜ?―風船とシャボン玉の熱力学と力学モデル
時計の正確さは何で決まる?―振動現象と単振動モデル
夏の鉄道のレールはなぜ伸びる?―調和ポテンシャルを超える近似
カオスとソリトン―非線形のままの振動モデル
アンテナはなぜ細長い?―多重極展開と双極子モデル
楽器の基音と倍音(1)―物体の振動現象のモデル
楽器の基音と倍音(2)―基準振動と物理現象
ヤモリとコウモリはなぜぶら下がれる?―法則とモデルの階層性(1)
GPSの生みの親はアインシュタイン?―法則とモデルの階層性(2)
著者等紹介
鹿児島誠一[カゴシマセイイチ]
1973年東京大学大学院博士課程修了。理学博士。同年電子技術総合研究所、1979年東京大学教養学部助教授、1982年パリ南大学客員教授、1988年東京大学教養学部教授を経て、2009年東京大学名誉教授、明治大学理工学部客員教授。2007~2008年日本物理学会正・副会長。主な研究分野は、有機導体の低次元電子系の物性(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。