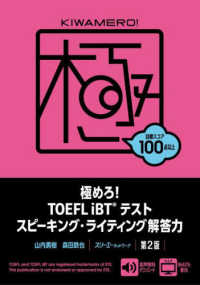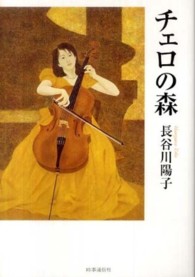内容説明
昭和を代表する知の追究者たちが、「学問の入り口とその世界」を語った伝説のインタビュー集。25年ぶりの復活出版。第三弾。
目次
服部四郎(言語学)日本語の系統を求めて
下村寅太郎(哲学)精神史の考え方から
梅棹忠夫(人文科学)私の知的生産の技術
渥美和彦(人工心臓)人は永遠に生きられるか
西郷信綱(日本古代文学)古典を『研究』から開放する
茂在寅男(航海史)ポリネシア人がカヌーで渡来した?
河合隼雄(心理療法)シンデレラの継母は教育ママ
小松茂美(古筆学)『平家納経』にかけた独学人生
加藤一郎(生物制御工学)ロボット作りの基本は手の動き
角田忠信(脳と東西文化)涙も笑いも左脳の日本人
著者等紹介
木原武一[キハラブイチ]
評論家・翻訳家。1941(昭和16)年東京都生まれ。東京大学文学部ドイツ文学科卒業。6年間会社勤務の後、文筆家として従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
May
4
初版(S55)再編集版(H21)。30人の碩学たちの研究者としての歩みや研究内容が語られるが、もちろん、専門知識なくとも理解できる内容。重要なのは書かれてある研究内容や成果ではなく、各人の研究姿勢等であろうから、再販当時ですらすでに陳腐化した研究内容であったとしても問題はない。私が文系であるからか知っているのは、江上波夫、山本七平、梅棹忠夫、河合隼雄のみだが、名前すら知らない理系研究者の研究内容もとても興味深いものがあった。高校生の時にこれを読んでいたら、私の進路は変わっていただろうか。2019/02/25
Eiko
2
1980年初版ですが、再編集を経て2009年に再出版された本。当時の一流知識人、ほとんどは大学を定年退職後の先生方に、生涯をかけて打ち込んだ研究や学問的興味を聞いたものですが、これが今読んでもものすごく面白い!! 残念な点を挙げるとすれば、それぞれの先生のページ数が少なく、「もっともっと話を聞きたい」と思わせるところで終わってしまうところでしょうか。「勉強するって、面白いんだな」と読者は感じるし、また自分ももっと勉強しなくてはと思わされます。2017/04/08
未来来
1
10人の研究者が「学問の入り口とその世界」を語ったインタビュー集。質疑応答形式ではなく、エッセイのようで読み易かったです。文系理系を問わない人選で、様々な分野を除く事が出来ます。研究に至る道筋も紆余曲折を得ていて面白いものがありますが、自分の知らない分野の研究方法が垣間見られるのが楽しかったです。《大学図書館》2009/08/20