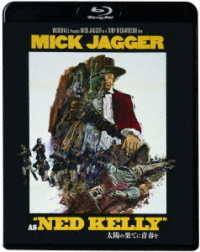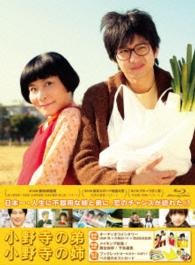出版社内容情報
《内容》 本書は,大学の学部学生,大学院学生,または機器や装置や分析法を初めて扱う研究者等を対象として,医学,薬学,農学,理学,工学などの生命科学に関連する物質を分子レベルで捉える「機器分析化学」の教科書である。
特色として,分析機器や装置や分析法の成り立ちと【社会との接点】,さらには【歴史】【方法】【装置】【操作と結果】【機構】【対象物質】の順に記載され,ブラックボックスである機器の性質などが簡潔にわかる点である。
取り上げる機器・装置と分析法は,物質の分離・精製・定量に用いるクロマトグラフィーなどの分離法,物質の検出・定量に用いる光分析法,共鳴吸収法,電気分析法,質量分析法,生物学的分析法,自動化分析法,高効率処理法,など全体を網羅している。
《目次》
1.分離分析法
1.1クロマトグラフ法
1.1.1液体クロマトグラフ法
1.1.2 ガスクロマトグラフ法
1.1.3 薄層クロマトグラフ法
1.1.4 向流クロマトグラフィー
1.1.5超臨界流体クロマトグラフィー
1.2 電気泳動法
1.2.1 等速電気泳動法、ゾーン電気泳動法
1.2.2.キャピラリー電気泳動法
1.2.3 等速電気泳動法
1.3 フローサイトメトリー
1.4.膜分離法
1.4.1.膜分離
(マイクロフィルトレーション、限外濾過、ナノフィルトレーション、逆浸透膜)」
1.4.2 マイクロダイヤリシス
2.光分析法
【社会との接点】
2.1.原子吸光光度法(フレーム、ICP発光)
2.2.紫外可視吸光度測定法
2.3.旋光度測定法
(旋光分散、円二色性)(屈折率測定法,偏光度測定法)
2.4.赤外吸収スペクトル法
2.5.蛍光分析法
(通常光、レーザ光、時間分解)
2.6.発光分析法
2.7.表面プラズマ共鳴
2.8.ミクロ顕微分析法
2.9.フローインジェクション分析法
3.共鳴吸収法
3.1.核磁気共鳴スペクトル法
3.2.電子スピン共鳴法
4. X線分析法
4.1. X線回折法
4.2. 蛍光X線分析法およびミクロ分析法
5.質量分析法
(各種イオン化法、MS/MSなど)
5.1.ガスクロマトガラフ法、液体クロマトグラフ法との組み合わせ
6.電気分析法
(酸化・還元分析法など)
6.1.pH測定法
7.生物学的分析法
7.1.バイオアッセイ
7.2 酵素を用いる分析法
7.3 結合タンパク質を用いる分析法
7.4 遺伝子の増幅を用いる分析法
8.その他の分析法
8.1.凝固点測定法
8.2.熱分析法
8.3.粘度測定法
8.4.比重・密度測定法
内容説明
生命科学物質を分子レベルで捉える「機器分析化学」教科書。分析機器・分析法の社会との接点、歴史、方法、装置、操作と結果、機構、対象物質の順に構成。機器分析のテクニックが簡潔にわかる。
目次
1 分離分析法
2 光分析法
3 磁気共鳴法
4 X線分析法
5 質量分析法
6 電気化学分析法
7 生物学的分析法
8 その他の分析法
著者等紹介
今井一洋[イマイカズヒロ]
東京大学大学院薬学系研究科教授
前田昌子[マエダマサコ]
昭和大学薬学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
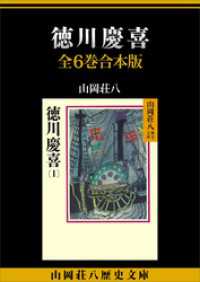
- 電子書籍
- 徳川慶喜 全6巻合本版 山岡荘八歴史文庫