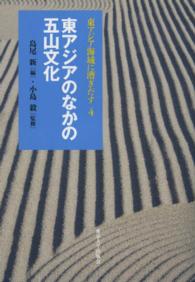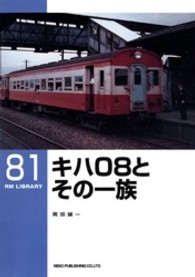内容説明
’68年5月革命によって、人類はユートピア論における新たなる水準を獲得した。著者はこのような視点からソ連・東欧革命を解読し、世界情勢論=体制論を展開する。
目次
1章 社会主義理念の崩壊
2章 東欧革命とユートピア的反乱
3章 出発点としての5月革命
4章 マルクス主義と収容所国家
5章 現代資本主義と消費社会
6章 群衆蜂起と分子革命
7章 ポストモダニズムと天皇制
8章 新保守主義時代の終焉
9章 世紀末とユートピアの冒険
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
HolySen
2
1968年前後の「第三世界革命」と思想を絡めることで、「マルクス葬送派」としての構造主義やポスト構造主義の思想の解説が分かりやすくなっている。グリュックスマン、ボードリヤール、ドゥルーズへの鮮やかな解説もさることながら、当時の社会や経済の情勢を絡めることで有機的な繋がりを以って(思想を社会と絡めて)マルクス以後の思想が理解できる。アナーキズムが好きにはなったけど、「革命」というユートピアがとても観念的なので、ある種のニヒリズムに陥っちゃうなあ。2015/03/17
毒モナカジャンボ
1
『構造と力』に代表される日本のポストモダン思想受容史において決定的に欠落した86年革命の体験。グリュックスマンはヘーゲルとクラウゼヴィッツの戦争論を対比し、無秩序を秩序化しようとする前者的な革命のあり方を否定する。ボードリヤールのマルクス読み直しは、生産=労働至上主義から消費主義への転換を生み出し、労働価値説より記号化された差異のゲームとしての象徴価値を見出す。DGのアンテオイディプスにおける分子革命の理論。筆者は三者を否定、実存者として敬虔な心を重視する。革命はユートピアとして瞬間的に生きられる。2020/06/24
西村修平(偽)
0
90年に出された本。マルクス主義批判から80年代のポストモダンの流行についての話が展開されている。カバ先生(笠井潔)と女子大生という対話形式の本なので簡単に読めるものだと想定していたが、結構難しかった。2017/01/01
床ずれ
0
ポストモダン思想の人々がいかにマルクスを乗り越えていったのかを理解。にしても対話形式なのがいちいち鼻について読みにくい。2015/08/14
もく
0
タハ、オモチロイ ニューアカ(ニュー赤?)の残り香のような出涸らしのような時期の出版だ2021/03/06