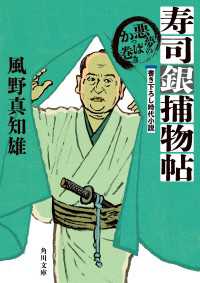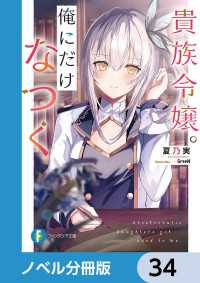目次
第1部 形成(グローバル経済史入門―世界の構造変動をめぐって;アジアとヨーロッパ―経済発展の国際比較 ほか)
第2部 一体化(開発と人口;グローバル経済の緊密化 ほか)
第3部 深化(グローバル経済の深化とライフスタイル;エネルギー)
第4部 展開(経済発展の多径路性;20世紀後半の展開 ほか)
著者等紹介
水島司[ミズシマツカサ]
1952年富山県に生まれる。1976年東京大学文学部東洋史学科卒業。1979年東京大学人文科学系大学院修士課程修了。同年、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助手同助教授、教授を経て、1997年東京大学大学院人文社会系研究科教授。博士(文学)。専攻:インド史、グローバル・ヒストリー、歴史地理情報システム
島田竜登[シマダリュウト]
1972年神奈川県に生まれる。1996年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。1998年早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。2001年ライデン大学アジア・アフリカ・アメリンディア研究所上級修士課程修了。2005年ライデン大学博士。2006年西南学院大学経済学部講師、同准教授を経て、2012年東京大学大学院人文社会系研究科准教授。専攻:東南アジア史、アジア経済史、グローバル・ヒストリー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
178
グローバル経済とは何か。元々アジアに圧倒的に押されていた西洋の経済競争力を支えたのは、新大陸の銀とアフリカ等の奴隷、それに大西洋やアジアに張り巡らされた運輸・経済網だった。初めインド綿布に太刀打ちできなかった西洋は、インド綿布に追いつくことを目標に、新大陸の綿を奴隷に栽培させ、やがて輸入代替工業化を成し遂げ、1820年英国がインドを追い抜く。今の暮らしは、文明やグローバル経済の恩恵を受けているが、大航海時代とそれに続く植民地支配や奴隷制度の歴史(日本もその跡を追った)を思うと、一杯の珈琲の味も複雑になる。2023/06/01
らっそ
5
プーチン政権の長期安定性は石油価格の高値安定にあるという視点。安倍政権も同じだったんだと思う2021/02/06
Hisashi Tokunaga
2
再試験を受験して高得点ゲット!昨年の問題よりやや易しかったか? インドがもつ世界経済史における役割が、いかんなく引き出される格好の初学者用教材かも。でも、一方試験にこんなにニッチな設問が用意されているとは!2019/01/31
icon
1
近現代のインドやアジアの経済史がご専門の水島先生の本が読みたくて選んだ本。近代的土地制度で、土地を担保にして借金・事業の勃興がおこって階層の二極化の遠因となり、共同体の崩壊が起こる。 ナットゥコッタイ・チェッティヤール(NC): 中間層移民の中で、東南アジアの開発の金融活動による下支えを担った、南インド出身の金融コミュニティ。アジア通貨危機が米巨大ファンドの空売りが原因とは知らなかった。 1939年代の南インド・タミルからの移動者の不可触民の割合。 径路、趨勢、オピアム2022/08/15