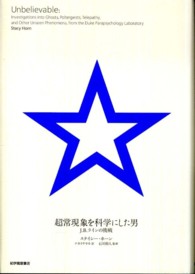内容説明
開祖がおらず、教養や救済もない。宗教の枠におさまらない神道について、歴史的な経緯、イスラム教との類似点、そして仏教との深い結びつきなど、「ない」宗教としての本質に迫る!
目次
第1章 「ない宗教」としての神道
第2章 もともとは神殿などなかった
第3章 岩と火 原初の信仰対策と閉じられた空間
第4章 日本の神道は創造神のない宗教である
第5章 神社の社殿はいつからあるのか
第6章 「ない宗教」と「ある宗教」との共存
第7章 人を神として祀る神道
第8章 神道は意外にイスラム教と似ている
第9章 神主は、要らない
第10章 神道には生き神という存在がある
第11章 伊勢神宮の式年遷宮はいつから行われているのか
第12章 救いのない宗教
第13章 ないがゆえの自由と伝統
第14章 浄土としての神社空間
第15章 仏教からの脱却をめざした神道理論
第16章 神道は宗教にあらず
第17章 「ある宗教」への胎動
第18章 「ない宗教」の現在と未来
著者等紹介
島田裕巳[シマダヒロミ]
1953年東京生まれ。作家、宗教学者。76年東京大学文学部宗教学科卒業。同大学大学院人文科学研究科修士課程修了。84年同博士課程修了(宗教学専攻)。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を経て、東京女子大学・東京通信大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
64
著者によれば、神道には開祖も、宗祖も、教義もないという。神社の中心には実質的には何もなく、神殿などもなかったのではないかと記す。しかし何もないが故に、日本に入ってきた「ある」宗教の仏教と、神仏混淆という形で両者は存在できたとも。少々割り切れないのは、弥生以前の神道、というより自然に対する畏敬の念あるいは畏怖の念といった、縄文以来の自然信仰?についての記述が何もなく、日本人の宗教観の最も根っこの部分が不明になっている感がすることである。「ない」宗教の最奥の部分が縄文に根ざしている、と思うのは私だけだろうか。2023/09/20
tamami
59
読書会の仲間から、「教義や救済の方法が無いといわれる神道に、それらを備えれば、一大宗教になるのでは」と問われ、言挙げしない神道などと答えたのだが、不明点を確かめるべく、本書を再読する。本書は、「ない宗教」としての神道の起源や「ある宗教」仏教との出会い、その後の歴史などにも触れながら、神道の本質に迫っている。そして、ないが故の自由と伝統について記すと共に、浄土空間としての神道のあり方を述べている。信仰する宗教については、「特にない」と答える人の割合も少なくないと聞くけれども、私たちは、初詣に始まる年中行事や2024/01/22
ころこ
52
10年前に出版された新書を改版して3度目の出版のようだ。著者が大切にしているように良く出来ている。神道は開祖も、宗祖も、教義も、救済も「ない」。いい加減で宗教に値しないと否定的にいわれる神道が、じつは世界宗教に駆逐されずに残った稀有な民俗宗教だという逆説的な肯定的評価を論じている。前半の神社探訪のような読み易い感じ、中盤の仏教の「ある」宗教との比較宗教学的な観点、後半の国学による近代性を獲得した肯定とナショナリズムに利用された否定の相反した観点と、小さな本の割には読むのも難渋で、内容が濃かった。2023/12/20
ヒデキ
52
増補版が出たことでやっと読めた1冊 「ない」宗教の「神道」が、日本に根付いていたために 「ある」宗教の仏教と共存していった姿は、確かに 判りやすい。開祖も教祖も無く「ご神体」というモノを拝み、願いを託す・・・ 一体、神道って何だろう?とある意味さらに分からなくなってしまいました。 確か、豊田有恒さんが、言われていたようにかっては、教えがあった宗教や祭事が、縄文・弥生と時代を経て忘れてしまわれ、形だけが残ったモノというとこなのでしょうか 「道」というだけ、宗教とは、違うモノなのでしょうね2023/09/23
ニッポニア
46
教えがない、と言うよりも万事に敬意を、という印象。以下メモ。神道における救いはひどく曖昧であり、宗教は救いを与えるもの、と言う定義では、神道に欠けている。神道を宗教の枠から外し、国民道徳や慣習として強制させようとする権力者の意図が働いていたのも事実。神道は意外にイスラム教と似ている。仏教の僧侶は修行を実践するが、神主は儀礼の執行者である。僧侶はプロフェッショナルだが、神主はあくまでアマチュアである。神道では神であっても仏教に縋るしか救われないことを意味している。ないがゆえの自由と伝統。ある宗教への胎動。2025/02/22
-

- 電子書籍
- 地獄祭【フルカラー】【タテヨミ】(34…