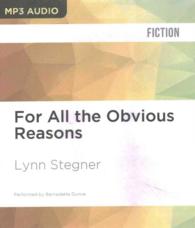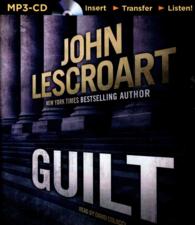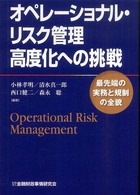内容説明
激動の大正時代が今日の日本の命運を決めた!?個性的で魅力あふれる、14年と5か月。大正時代に惚れる。
目次
第1部 新しい時代、始まる(漱石の「明治」への哀惜―天皇崩御で「時代は終わった」;新時代への拒否反応―消し去られる武士道に怒る鴎外 ほか)
第2部 庶民の力、漲る世相(即位式と東京駅―新天皇、熱烈歓迎の中を京都へ;外国から千客万来―余裕と自由で受け入れた社会 ほか)
第3部 華ひらく大正文化(タカラヅカの誕生―私鉄開発が生んだ日本的歌劇;「赤い鳥」の時代―あふれていた子供たちの文学 ほか)
第4部 大正時代の陰と終焉(天皇の病状悪化―悲痛な報告に悩む首相や元老;皇太子の訪欧―反対押し切りイメージアップ ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
柳 真佐域
15
大正時代を知るために読んだ本第2弾。前回に比べ文章が興味を引かせるように書いてあるので格段に読みやすかった。前半から中盤にかけての天皇、政治の動きも知れて良かったが後半にかけての文豪や教育、庶民の文化を知れたのは大きい。「新しき村」や自由教育の前身である「椎の木学校」などネタになりそうなものも見つけられた。しかし、図書館で借りてきたにも関わらず、皇国の守護者3巻が面白すぎて遅々としてページが進まなかった。演歌は演説の歌だから演歌らしい。寝ずの研究する野口英世が米国人から「二十四時間人間」と呼ばれていたエピ2019/04/10
湯一郎(ゆいちろ)
6
なんとなくぼんやりしていた大正時代へのイメージがついた。絶大な人気を誇った明治天皇の崩御から始まって、気さくな天皇陛下にバトンタッチ。人気のある宰相として大隈重信、原敬などがいて、その裏で強い影響力を維持する山縣有朋が椿山荘から睨みを利かせて、大衆は大戦景気とデモクラシーでなんとなく浮かれて、雑誌がたくさん創刊されたり、宝塚も始まったりして、でも大正天皇はご病弱で…。そして普通選挙法と治安維持法が成立して昭和へ。なるほどなるほど。明治と昭和の橋渡し。2019/02/14
ささ
2
■表紙を見て、大正時代の文化を扱っているのだろう、と手に取ったら、文化だけではなく、政治・経済についても、大いに触れられていた。1つのテーマにつき、4ページほどでまとめられているので、さらっと読める。気が合わないであろう、山県有朋と原敬。しかし、原敬の死を山県有朋が非常に惜しんでいた、というエピソードが、少し意外に思えた。2014/01/26
akiu
2
大正ネタ収集のために読みました。元が新聞の連載記事であるせいか、文章が簡潔にまとまっていて読みやすかったです。特に政治・経済の辺りがよく書かれていると思いました。読む前の雰囲気は、もっと生活に根ざしたエピソードが多そうな感じがしていましたので、ちょっと肩透かしの感もありましたが(表紙とかタイトルから、そんな印象を受けていたもので…)、これはこれで興味深いエピソードがいくつか。2012/02/06
浮舟りつ
1
大正時代に生きた人々の生活感を知りたくて読んだ。政治、思想、文化全般に渡ってとても公平にかけている良書だ。1トピック4ページというのも寸暇で読み進められるのが良い。図書館から借り出し。2017/05/05