目次
序論 丼家の店舗
第1章 店舗の儀礼
第2章 店舗の管理
第3章 組織の窮状
第4章 経営の極意
結論 丼家の経営
補論 丼家の系譜
著者等紹介
田中研之輔[タナカケンノスケ]
1976年生、一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。メルボルン大学大学院社会学プログラム客員研究員、カリフォルニア大学バークレー校大学院社会学専攻客員研究員を経て、法政大学キャリアデザイン学部准教授・株式会社ゲイト社外顧問。専攻は社会学・社会調査論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Nobuko Hashimoto
31
研究者の友人に教えてもらって数年寝かしていたのをようやく。丼を出す外食産業を何店も食べ歩いたりアルバイトとして働いたり、インタビューをしたりしたフィールドワークをまとめたもの。著者は、ブラックな働き方を炙り出すことになるかと思ったが、マネジャーらの人間関係の構築がうまくいくと滑らかな店舗経営となるということがわかったという点を強調しているのだが、そのマネジャーらが続々辞職して他業種へ転職しているという事実は、経営上の大きな失敗なのではないだろうか。2023/07/15
苦虫
8
【マーカー済】教授より。まず、これは牛丼チェーン店へ消費者、労働者として参与観察と聞き取り調査を行い、学術的な知見の上に成り立っているエスノグラフィーである。「牛丼屋はなぜ儲かるのか?」的なビジネス本ではない(もちろん、ドラッカー的な経営学の視点はふんだんにある)。社会学棚ではなく、ビジネス書の棚に並べた書店員、ちょっと正座しなさい。脱人間化されたチェーン店ではマネジャーのマネジメントの元、人間化への工夫がなされて利益が発生する。リッツァ、ミルズ!一方で、24時間体制への限界もある。非常に刺激的な本。2015/04/16
ぷほは
3
くそ面白かった。もう自分がやりたいと最近思っていたことは、ほぼ全てこの本でやりつくされている。経営学や実務経験をふんだんに織り込んて、なおかつ「社会学」としか言い様がない切れ味鋭い記述。ただ、最後らへんからやや話が一面的になっていったように思われること、結論があまりハッキリしたものではないこと、文中にフィールドノーツやインタビューの文章をそのまま草稿の段階で載せているのではないだろうか、と疑ってしまうほど文体が乱れ気味になることなどが、やや残念に思う。最後の点はむしろリアリティを担保させるものなのだが。。2016/06/11
wang
1
「丼物屋で働く人々」。著者自身がアルバイト店員として複数チェーンで働き、あるいは実際に働いている人々へのインタビューをまとめたもの。各発言や行動の説明としてミンツバーグらの著書のどの部分に相当するかが注記されている。24時間営業の牛丼チェーン店ではアルバイトやパートの店員の採用、シフト調製、教育、人間環境の配慮、モチベーションコントロールが非常に重要。個人の実体験に基づく生の声は様々でリアル。だが、メニューについても調理についても立地・資金等々人間関係以外を無視している。フィールドワークの素材だけ。2016/07/19
げんざえもん
0
ビジネス書としても、パート主婦による熱血店舗再生物語としても面白い、読んで楽しい学術書(質的調査によるエスノグラフィー)。生活費の足しにとパートとなった主婦が、熱意と能力でエリアマネージャーに抜擢されて不採算店を熱血指導、世界最強のサッカーチームのような流れる連携プレーで牛丼を提供して売上記録を連続更新! マネージャーたちの聞き取り調査が熱すぎる! 誰かドラマ化しないかな…2025/04/02



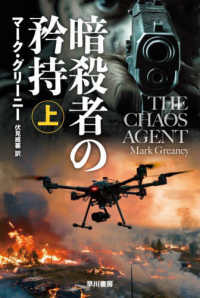

![のりものすごろくバラエティセット [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/43300/4330003228.jpg)



