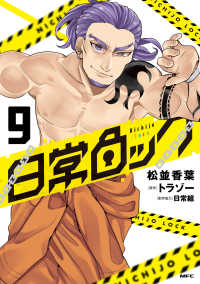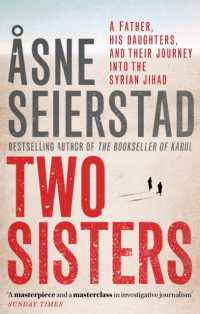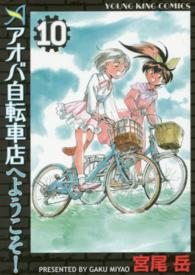内容説明
ノーベル賞作家の愛と勇気の手記。“いつまでも子どものままの”わが娘と歩んだ母親パール・バックが、知能の発育が困難な子どもへの社会の無理解と偏見に悲しみ苦しみながら、人間性の尊重を真摯に訴えた不朽の名作。
著者等紹介
バック,パール[バック,パール] [Buck,Pearl Sydenstricker]
1892‐1973。アメリカの作家。ウェスト・ヴァージニアに生まれる。生後まもなく宣教師の両親に連れられて中国に渡り、アメリカの大学で教育を受けるため一時帰国したほかは長く中国に滞在し、その体験を通して、女性あるいは母親としての目から人々と生活に深い理解をもって多くの作品を発表した。1932年に『大地』でピュリッツァー賞を、38年にはノーベル文学賞を受賞。また1941年に東西協会設立、48年にウェルカム・ハウスの開設と運営に尽力するなど、人類はみな同胞と願う博愛にみちた平和運動家としても活躍した
伊藤隆二[イトウリュウジ]
1934年生まれ。東京大学教育学部卒業、同大学大学院修了。教育学博士。カリフォルニア大学(UCLA)留学。神戸大学教授、横浜市立大学教授を経て、横浜市立大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
64
半生を懸けた”環境”改善への取り組み。孤立感が随所に滲む時代背景と、著者自身の受容までの精神的葛藤は計り知れない。転機は著名なメイヨー病院でのドイツ人医師との出会い。文字通り、悲しみとの融和の旅の始まり。二度目の転機は、娘の手の汗。権利、平等、幸せ。求める姿勢から見出す姿勢に変化した気がする。それが表題であり、同じ境遇の(父親と)母親へのメッセージ。知人に薦められるまま手に取ったため、当初は小説と勘違い。様々な意味での先駆者として、著者が遺した功績(精神性)は、次世代に受け継がれていると信じたい。 2019/08/07
ロビン
15
中國で長く生活したアメリカ人ノーベル文学賞作家パール・バックが、知的障害を持って生まれた一人娘キャロラインさんのことを綴った本。知的障害の家族を持つことは、認知症の家族の介護同様に、本当にきれいごとでは是非を論じることはできないと思う。「この子が死んでくれたらと思うことがある」とまで、バックは非常に率直に勇気をもって自分の本心を語っていると感じた。知的障害はない方がよい、としながらも、キャロラインさんだけが果たすことのできる使命、彼女が生まれてきたことの意味をバックは懸命に見つけ出そうとしたのだ。2024/12/31
ケニオミ
11
一人娘が障碍児であったパール・バック女史。彼女がどのように娘の障碍を受け入れたのか、どのような基準で娘を託す施設を選んだのか、そして、娘との離別をどのように克服したのかを綴ったお話です。先に死んでいく自分の死後、娘が一人で生活できるように考えた結果、施設に預ける選択をするバック女史。彼女とは次元が違いますが、同じく娘を一人もつ親として、彼女の気持ちが痛いほど分かりました。「文明の程度は、それが弱い人、頼るところのない人をどのように尊重しているかによって測られる」という女史の言葉が印象的でした。お薦めです。2013/12/02
たくぼ
7
知的障害児を持つ母親への長いエール。1930年当時は、ずいぶん苦労されたのだろう。時代が変わっても苦労や悩みは変わらないのだろう。書かれていることには全く異論は無いのだが、子どもがいない私は、どうしても社会生活に置き換えてしまい、多様性を尊重するために社会は(会社では)何が正しいのかを考えてしまう。知的障害と多様性は別物と切り分けるべきなのだろうけれど。生きているすべての人は幸せになる権利を持っている。その権利を社会、周囲はそのように尊重するかってことだな。★★★★2021/06/21
さとう
5
松岡久子訳で読了。 "いかなる人でも、人間である限り他の人々より劣等であると考えてはならないこと、そして全ての人はこの世の中でその人の住むべき場所と安全を保護されなくてはならないと思うようになったのであります。もし私がこれを理解する機会に恵まれなかったとすれば、私はきっと自分より能力のない人に我慢できない、あの傲慢な態度を持ち続けていたに違いありません。娘は私に、人間とは何であるかということを教えてくれたのでありました。"2019/10/31