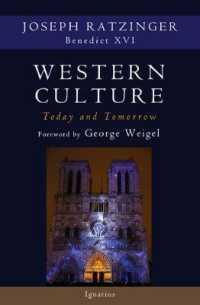目次
第1部(オシンコウ二皿ください;石のようになった人;わたしの「友だち」;かのさんのカロ;はるさんのクロカゲ;ひと山越えても鹿おらん;エゾと呼ばれた人たち;みはるさんの『冬の夜ばなし』)
第2部(寂寞ということ;「捨てる」ということ;母なるもの、子なるもの;「現代の民話」について;一粒の豆を握る・一粒の豆を見失う;「ふしぎ」の根をさがす;山の民について―猿鉄砲のむかし;浜で出会った人たち;ゆめのゆめのサーカス)
著者等紹介
小野和子[オノカズコ]
民話採訪者。1934年岐阜県生まれ。1969年から宮城県を中心に東北の村々へ民話を求めて訪ね歩く民話採訪を一人で始める。1975年に「みやぎ民話の会」を設立し、現在は同会顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いちろく
26
紹介していただいた本。一軒一軒現地を訪ね、人から人へ語られてきた民話を直に伺い採取してきた著者。本書は「みやぎ民話の会」の設立者でもある著者の50年に及ぶ民話採集の一端を描いた内容。主に描かれるのは1970年代から80年代の頃であり、本書によるとテレビの存在により家族間の民話の伝達が途絶える頃でもあった時期。語られる内容の背景、由来の解説により、また別の物語が見える状況もあり、読みながら唖然としたことも多々。確かに今では多くが失われてしまった口伝の一部の記録とも思えた。2024/06/28
bluemint
22
著者が自分の足で聞き集めた民話の数々。中にまだ熟成していない断片や、「できごと、事件」みたいなものも含まれていて「話」になるまでの過程が想像できる。合間には話の採集時の苦労や歓迎されて楽しかった事などが記録されている。真夏の暑い山路を歩き続ける著者の姿が目に浮かんだ。ただ、肝心の「話」の部分がやっと読めるかどうかくらいに薄い色の印刷になっているので、物凄く読みにくい。目が良くないので、これには困った。どういうわけなんだろう?読者のことを考えない独りよがりの装幀としか思えない。2024/07/09
昭和っ子
20
著者の栽話への憑かれたような情熱には、やはり「終戦」にまつわる幼少時の思いがあるようだ。著者の年齢は私の親世代だが、皆働く事に忙しそうな人ばかりだった(そのお陰で今日の繁栄がある)。著者は心のままに彼らに代わって、断絶された昔の縁を求めて歩き回ってくれた人なのだろう。集められたお話は、投げつけられた断片のようなものばかりだが、語り手と聴き手の深い交わりの中から、驚くような深みを持って意味が立ち現れる様が記録されていた。2021/10/17
べる
18
「子どもの頃に聞いて覚えている昔話があったら、聞かせてくださいませんか」肩書きも職業もない四十歳の女性がノートを持ってふらりと訪ねる。宮城県の小さい集落から始まった筆者の五十年に及ぶ民話採訪。口と耳だけで営まれた物語世界。背景には必ずそれを語ってくれた死者がいて、その人への思いがあるから「言葉」は命をもって昔と今を繋ぎ、無限の未来を生きる。語り継ぐ間に欠落や取違えなどの変化があって語り手の暮らしが見える面白さもある。違う話でも、魂の繋がりを信じる心がある日本人の共通性が見えてじーんとくる話もあった。深い。2023/01/17
まあやん
16
著者は採話ではなく採訪と言っておられる。その人の生活や思いも一緒に拾い上げられていて、私の昔話のイメージとは違い、湿り気のある重たい感じがした。稲田浩二さんが、民話は温かい家庭、生活の安定を土台にして伝えられると言われたそうだ。私の昔話のイメージもそういうものだったが、ここでは生活の苦しさ故に伝えられた民話が多い気がした。「猿の嫁ご」を語られたヤチヨさんが、猿が川へ落ちたところが好きだという。猿がかわいそうと思いがちだが、辛いことも多かった嫁はそんなことは思わないんだな、きっとスカッとしたのだろうな。2021/05/04
-

- 和書
- モンテカルロ法入門