内容説明
浦々や港の様相、景観に目配りしながら、中世の瀬戸内海にひしめく大小さまざまな海賊の姿を描きだす。
目次
序章 ある禅僧の船旅―海賊の周辺
第1章 東国武士、海賊になる―安芸国蒲刈島と多賀谷氏
第2章 南朝の海上ネットワーク―伊予国忽那島と忽那氏
第3章 港を支配する海賊―備後国鞆と因島村上氏
第4章 港を要求する海賊―周防国秋穂と能島村上氏
第5章 海賊の船
終章 港から港町へ―安芸国瀬戸田と生口氏
著者等紹介
山内譲[ヤマウチユズル]
1948年生まれ。京都大学文学部史学科卒。愛媛県内の県立高校教員を経て、松山大学法学部教授。専門は、中世瀬戸内海地域史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なつきネコ@着物ネコ
3
〇瀬戸内海が、どれだけ大事な水路であったか、わかった。しかし、驚いたのは足利義昭がともに対して、とも幕府めいた物を地方に作りだしている事。本当に足利義昭はしぶとい。さらに数々の海城は現在はなくなっている事実は悲しい。瀬戸内海が舞台だけあって、小早川氏の関連は大きいし、そう言った大名関でしか彼らの姿を知れない。2014/03/03
イツシノコヲリ
2
中世の芸備諸島の港について興味があったので読んだ。因島村上氏の視点から見た鞆の浦の論考や「兵庫北関入船帳」によく登場する瀬戸田の景観の論考が興味深い。周防の上関や秋穂についても触れられている。また中世の海賊の軍船についての論考が面白かった。安宅船という構造的な視点からの船の呼び方は、海賊には使われなかったのこと。2022/11/12
-
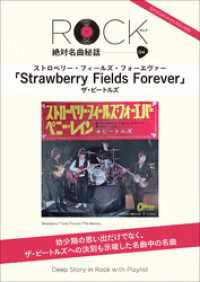
- 電子書籍
- 「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴ…
-
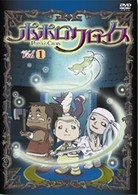
- DVD
- ポポロクロイス Vol.1






