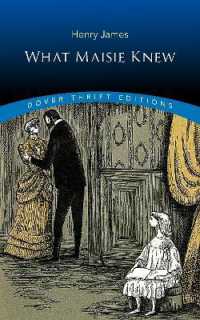出版社内容情報
経験と観察に基づく〈人間の学〉を目指し、観念・記憶・想像・感覚・印象・信念・習慣・人格の同一性等々広範な精神領域を考察する。イギリス経験論哲学の最高峰。待たれていた普及版、ついに刊行はじまる。
内容説明
無名の青年が匿名で約300年前に出版した本書は、当時の常識に反するものとして激しい批判を浴びる。しかしその後の思想家に多大な影響を与え続け、西洋哲学の主著となった―。
目次
人間本性論
第1巻 知性について(観念、その起源、複合、抽象、結合等について;空間および時間の観念について;知識と蓋然性について;懐疑論的およびその他の哲学体系について)
解説(デイヴィッド・ヒュームの生涯と著作;ヒューム『人間本性論』の理論哲学)
著者等紹介
木曾好能[キソヨシノブ]
1937年大阪市に生まれる。京都大学文学部卒業。京都大学文学部教授。イギリス経験論哲学と現代分析哲学を専門とし、代表的論文に「心とは何か 1・2」(『京都大学文学部研究紀要』26・27号、1987・88)「個物と普遍」(『新岩波講座哲学』第4巻、1985)などがある。1994年死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buuupuuu
20
知覚、すなわち、私たちが感じたり考えたりするものはすべて、源泉に遡れば感覚に行き着くという考えを徹底している。そして、私たちが非哲学的な状態のとき、実際にはどのような仕方で、どんな内容の認識を抱いてるのかが説明される。後の時代に分析的/総合的などとされるような区別がなされており、このうち総合的と呼ばれるようなものの認識や意味理解において主に哲学的困難が生じることが論じられている。ヒュームは、哲学的反省を反自然的なものと見ているが、自然な傾向には迷信なども含まれており、反省を迷信に対抗するものと考えている。2024/11/13
ポルターガイスト
3
感染症より人間が怖い。「五輪があるから緊急事態宣言に効果が出ない」とか「○○知事の政策が原因で△△が生じているのだ」とか言う人たくさんいるが,本当に?その因果関係はどうやって論証されたの?実は情念や信仰が先にあって,理性(reason)による推論は後付けの虚構なんじゃないの?そう思ってしまう。だから政策の是非なんかより先に,そもそもの人間の認知のしくみ・幅を知りたくなる。ヒュームもそんな悩みを持った人だったのではないか。世の中ここまで誠実な人も一応いた,それを確認できただけで,気持ちが落ち着きました。2021/05/03
Yoshi
0
読みにくい本ではない。難解という感じでもない。ですが、分厚く、読むのに苦労する本ではある。当時の哲学者の本は、科学的に人間や認識を扱おうという姿勢が見られる。チョムスキーが、書籍「言語の科学」の中で、ヒューム以降の認識論は退化しかしていないと書いていた。。。