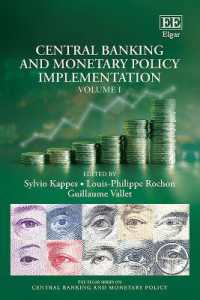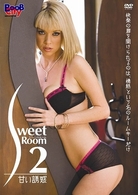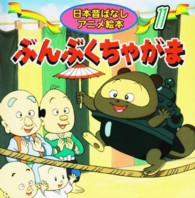出版社内容情報
私たちの民族、私たちの領土、私たちの国家と名指すとき、あるいは私たち労働者、私たちマイノリティ、私たちサバルタンと名のるとき、そこには政治が生まれ、歴史が前景化する。人びとを団結させ同時に分断する、多義的かつ可塑的なこの〈私たち〉という言葉のありようを哲学的に分析する気鋭の挑戦。世界中で同一性をめぐる戦争が繰り広げられる今こそ読まれるべき現代思想の最前線がここにある。
【目次】
第一部 透写紙
一人称複数
万物─私たち─私
三つの反論
私は私
私たちみんな
〈利害に基づく私たち〉と〈理念に基づく私たち〉
どんな私たちも分割システムである
分割の争い
交差点のモデル
透写紙のモデル
輪 郭
部分重複
半透明と不透明
被 覆
基 盤
第二部 制約
第一章 私たちの基盤
種
ジェンダー
人 種
階 級
年 齢
解体のプロセスの一般的物語
第二章 力学
理想主義の約束
キリスト教の約束
共産主義の約束
進化論的楽観主義
現実主義による事実確認
歴史的な事実確認
政治的な事実確認
隣人への攻撃性
延長と強度の力学
〈私たち〉は決して〈私たち自身〉と一致しない
第三章 支配
非対称性
不平等における平等
〈私たち〉の内なる〈彼ら〉
支配の必然性
解放の必然性
現実的支配、支配の効果、被支配感覚
戦略的マイノリティ
闘争の場としての支配の歴史
〈私たち〉の〈私たち〉に対する戦争
第四章 〈私たち〉の終わりと目的
謝 辞
訳者解説
内容説明
私たち労働者、私たちマイノリティ、私たちサバルタンと名のるとき、私たちの民族、私たちの領土、私たちの国家と名ざすとき、〈私たち〉と〈彼ら〉を分かつ境界線が引かれる。〈私たち〉の戦争を終わらせるために。実体なきアイデンティティの政治に抗い、無数の〈私たち〉、私たちではない〈私たち〉を想像してみよう。思弁的フィクションを超えて新たな連帯のイメージを描く、哲学の挑戦。
目次
第一部 透写紙(一人称複数;万物‐私たち‐私;三つの反論;どんな私たちも分割システムである;分割の争い;交差点(インターセクション)のモデル
透写紙のモデル
輪郭
部分重複
半透明と不透明
被覆
基盤)
第二部 制約(私たちの基盤;力学;支配;〈私たち〉の終わりと目的)
著者等紹介
ガルシア,トリスタン[ガルシア,トリスタン] [Garcia,Tristan]
1981年、フランス生まれの哲学者、小説家。高等師範学校およびソルボンヌ大学で哲学を学び、ピカルディ大学で博士号を取得。現在、パリ国立高等美術学校教授。小説La Meilleure Part des hommes(´Editions Gallimard,2008)でフロール賞受賞、小説M´emoires de la jungle(´Editions Gallimard,2010)でポンティヴィ歴史小説ビエンナーレ賞受賞
関大聡[セキヒロアキ]
ソルボンヌ大学文学部フランス文学・比較文学科博士課程修了。専門はフランス文学、フランス思想、実存主義。現在、日本学術振興会特別研究員PD、立教大学文学部兼任講師、放送大学などで非常勤講師
伊藤琢麻[イトウタクマ]
専門はフランス文学、フランス現代詩、トリスタン・ツァラ。論文に「トリスタン・ツァラにおける「近似」の概念」(『早稲田大学文学研究科紀要』第63輯、2018年)、「危機の時代と詩の探究―1930年代中頃のトリスタン・ツァラについて」(『WASEDA RILAS JOURNAL』No.8、2020年)「バンジャマン・フォンダーヌ『亡霊たちの悲痛』の中の実存とポエジーの働き」(『早稲田大学文学研究科紀要』第68輯、2023年)などがある。ソルボンヌ・ヌーヴェル大学博士課程在籍中、2024年に逝去
福島亮[フクシマリョウ]
東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程単位取得満期退学。専門はフランス語圏カリブ海・アフリカの文学と思想、および「第三世界」の文化運動。現在、富山大学学術研究部人文科学系講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラウリスタ~
Go Extreme
ありえない犬
-
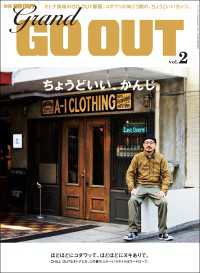
- 電子書籍
- GO OUT特別編集 GRAND GO…