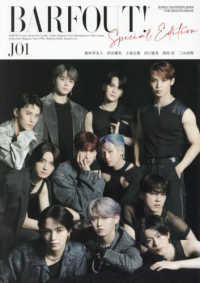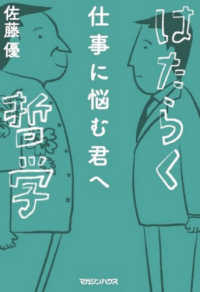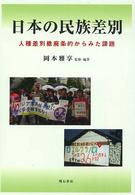内容説明
フーコーの“まなざし”の概念を手がかりに、ツーリストの視線とその対象を歴史的・経済的・文化的・視覚的なさまざまのレベルにおいて分析。グローバル化、デジタル化、景観破壊、環境問題のリスク、“負”の観光…現代社会の重要課題から見えてきた問題点を、最新の観光理論とともにあらためて論じ、人間の営為の変容にともなう新たな課題を提示する。
目次
第1章 観光理論
第2章 大衆観光
第3章 経済
第4章 労働とまなざし
第5章 観光文化の変容
第6章 場と建造物とデザイン
第7章 見ることと写真
第8章 パフォーマンス
第9章 リスクと未来
著者等紹介
アーリ,ジョン[アーリ,ジョン] [Urry,John]
ケンブリッジ大学で経済学修士、同大学で社会学博士号取得。ランカスター大学勤務。教授、学科長、初代社会科学部長、大学研究所長を務める。王立芸術協会会員、学士院会員、英国社会科学協会会員であり、また、英国国立航空研究所主任研究員などを務めた。現在ランカスターの“移動の科学研究所”所長
ラースン,ヨーナス[ラースン,ヨーナス] [Larsen,Jonas]
ロスキレ大学(デンマーク)の地理学担当講師。専門分野は移動の科学、観光旅行とメディア。観光旅行、地理学と移動性の研究誌での論文多数
加太宏邦[カブトヒロクニ]
大阪外国語大学(現・大阪大学)外国学部大学院、ジュネーヴ大学、ローザンヌ大学で学ぶ。法政大学名誉教授。専門は文化表象論、観光文化論、スイス文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
富士さん
Shiori
ノーマン・ノーバディ
かぺら