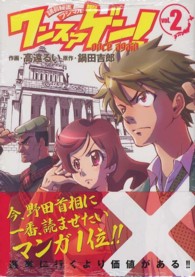内容説明
ルネッサンス期以降、学問としての美術史はいかなる知の言説として確立されたのか。ヴァザーリによる人文主義的美術史の発明から、パノフスキー的イコノロジーの成立にいたる美学の歴史を、表象の裂け目に現れるフロイト的「徴候」への眼差しを通じて批判的に解体する“美術史の脱構築”。バタイユやヴァールブルクを継承し、独自のイメージ人類学を実践する注目の美術史家の初期代表作。
目次
提起される問い
第1章 単なる実践の限界内における美術史
第2章 再生としての芸術そして理想的人間の不死性
第3章 単なる理性の限界内における美術史
第4章 裂け目としてのイメージそして受肉した神の死
補遺 細部という問題、面という問題
著者等紹介
ディディ=ユベルマン,ジョルジュ[ディディユベルマン,ジョルジュ][Didi‐Huberman,Georges]
哲学者、美術史家。1953年6月13日生(サン=テティエンヌ,フランス)。リヨン大学で哲学の学士号を取得した後、美術史学の修士号を取得。その後、社会科学高等研究院(E.H.E.S.S.)で博士号を取得。1990年から社会科学高等研究院の助教授
江澤健一郎[エザワケンイチロウ]
1967年生。明治学院大学文学部フランス文学科卒業。立教大学大学院文学研究科博士課程後期課程満期退学。博士(文学)。現在、立教大学ほか非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。