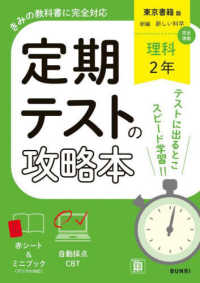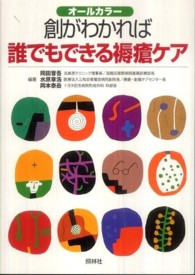- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
「映画」を思考することによって「運動」や「時間」をめぐる哲学の概念を新たに作り直す。ドゥルーズの真に創造的な傑作。
目次
運動に関する諸テーゼ―第一のベルクソン注釈
フレームとショット、フレーミングとデクパージュ
モンタージュ
運動イメージとその三つの種類―第二のベルクソン注釈
知覚イメージ
感情イメージ―顔とクロースアップ
感情イメージ―質、力、任意空間
情動から行動へ―欲動イメージ
行動イメージ―大形式
行動イメージ―小形式
フィギュール、あるいは諸形式の変換
行動イメージの危機
著者等紹介
ドゥルーズ,ジル[ドゥルーズ,ジル][Deleuze,Gilles]
1925年生まれのフランスの哲学者。1969年からパリ第八大学教授をつとめる。ドゥルーズは概念の創造に哲学本来のあり方を探り、自ら概念を新たに創造することによって哲学を作り直そうとした。1995年11月4日死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
wadaya
11
若い頃、映画学校に通っていたことがある。映画を志すと必ず打ち当たる壁がある。純粋に映画が好きで入って来た者も、僕のように映画をアートと考えている者にも等しく「商業的」な壁が立ち塞がる。最終的に学校を卒業した者は半数以下、映画産業に進路を求めた者は数えるほどしかいない。私も映画の道には進まなかった。ドゥルーズは序文で既に私の気持ちを代弁してくれている。「映画作りの桁外れに大きな部分がくだらないものであるが、偉大な映画作家たちは他の芸術に比べ外的要因に潰されやすいというだけで、私たちに程度の差こそあれ偉大な→2020/04/30
明石です
6
一冊の本と格闘したという感じ。疲れた。死んだ。2025/10/26
ぴこ
3
冒頭でこれは映画史ではなくイメージの分類学だと宣言されているが、歴史的な順序に従って分析されているように見える。そこが批判される所でもあるんだけどドゥルーズの隠れた意図があるような気もする。とにかく参照される映画の数が半端じゃない。何度もベルクソンの物質と記憶に戻る必要があるし、パースも読んでおきたい(読んでないけど)。黒澤がシチュエーションのデータを問いのデータに高めたと論じてるところでぐっときた。2017/03/31
uchiyama
2
全編容赦無しのトップギアなんで、ほぼ発進不能、という感じでしたが、ここまで読む方の知性を信頼するやり方は、ゴダールに通ずるものがあるなと思いました。(そんな信頼には全然応えられない…ってところも。)それでも一番わくわくとしたのは、「知覚イメージ」の章で、「内容の自律的なヴィジョンとして打ち立てられる或る純粋な〈形式〉に向かって、主観的なものと客観的なものとを止揚する」って、感動したあれやこれやの映画を思い出したりしました。また折に触れて読み返したいと思います。2024/08/12
コタロー
1
よくわからんとこのほうが多かったがさしたる問題もなし。とりあえず下巻へ向かう。2014/09/02
-

- 電子書籍
- 【単話版】外科医キアラは死亡フラグを許…