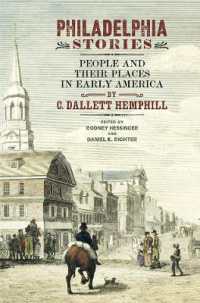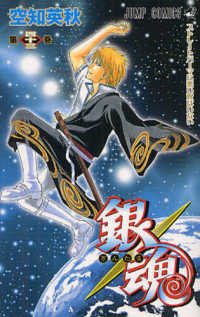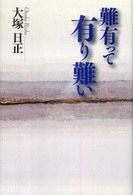内容説明
『源氏物語』の作者として誰もがその名前を知っている紫式部。これまで詳しく知られていなかった、彼女の生涯と人間像を、『源氏物語』『紫式部日記』『紫式部集』を中心に、系図や当時の記録類、交友関係などから、明らかにする。また、『源氏物語』を読む上で、知っておくとより物語が楽しめる、10のエッセンスも紹介。平安文学研究・源氏物語研究の第一人者が、紫式部と源氏物語の魅力を余すところなく伝える。
目次
第1部 深掘り!紫式部(従来の紫式部像;学才に対する自負;家系と家庭環境;娘時代の体験と性格;恋愛・結婚・出産・死別 ほか)
第2部 深掘り!源氏物語(「桐壺」の巻は初めの巻?;「かざり」とは?;登場人物の消滅と再生;『源氏物語』の短文表現;『源氏物語』の遡及表現 ほか)
著者等紹介
中野幸一[ナカノコウイチ]
早稲田大学名誉教授。文学博士。専攻は平安文学。2011年瑞宝中綬章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroh
27
深掘りというだけあって他の本にないことも書かれていて面白かった。宣孝とは初婚じゃない? 式部の方が積極的な恋歌、そして相手にすっとぼけられる。世の中を憂しと思うだけではなく、そう思いつつもその世で生きていかなければならない自分を見つめる目。雨夜の品定めの左馬頭ら、活躍しそうでそのまま消えてしまう登場人物。平安貴族じゃないとわからない描写の隙間。夕顔と某院へ行った時など極少人数に見えて、実は灯りを持った先駆けや後方の随身がいた。格子戸は大きく重いから「手づから開けた」と書いてあっても一人でしたわけではない。2023/06/29
お涼
21
江戸時代の学者が著した『紫家七論』で語られる紫式部のイメージが通説となっているという。本著はそれにとらわれず『源氏物語』や『紫式部日記』を元に紫式部自身や物語について深掘りしている。いつの時代の人にも惹かれて止まない『源氏物語』。知っていたエピソードもありつつ、短文の使い方や二次創作作品の存在など興味深かったし、御簾や格子の扱い方など言われてみれば、と面白かった。【図書館本】2023/12/09
とと220
5
高校以来久しぶりの古文を読み、声に出して読んでみたり楽しかった。2024/01/24
plum
1
文芸的な血筋。生活と観察眼。「憂し」の型p53深遠で複雑。式部の憂愁の度合いは,宣孝との死別を主因とする従来の厭世観に加えて,さらに宮仕えがもたらした違和感,疎外感,劣等感,孤独感等が相乗しあって深化されていくp67。年立:物語の展開を主人公の年齢を軸として年表化したものp78。「かざり」「短文」「草紙地」など式部独特の特徴を知ることで面白さが増す。短編から長編(合体合成?)へ。貴族の生活習慣への理解と同時期に存在した他の物語の影響も加味されたい。2024/08/11
NATSUMI
1
図書館本。大河ドラマに向けて借りてみた。最後まで読めず、、、。まだ源氏物語を全て読めてない私には早かった!2023/07/28