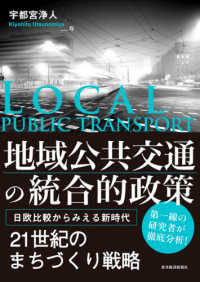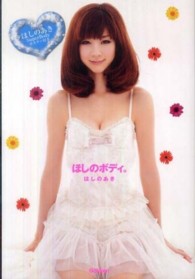内容説明
鎖国下、出島のカピタン(オランダ商館長)が日蘭貿易の継続を求め、166回に渡り行った「江戸参府」。その最後の旅でカピタンが目にしたものは何か?参府一行に出会った各地の役人や町人・村人の反応はどうだったのか?将軍への謁見の様子、献上物や買物、阿蘭陀宿での盗難事件など、多数のエピソードを紹介しつつ、江戸幕府の対外政策の実態を解明する。近世史・交流史・文化史・風俗史研究に有益な一書。
目次
第1章 江戸参府史料を日・蘭双方にもとめてみると
第2章 江戸参府一行の顔触れ
第3章 レフィスゾーンの江戸参府・往路
第4章 江戸滞在と将軍謁見
第5章 レフィスゾーンの江戸参府・復路
第6章 五都市六軒の阿蘭陀宿
第7章 幕末、異国人、日本を旅する
第8章 そして、新たな問題
附録 ケンペルの描いた「蘭人御覧」の部屋はどこか
著者等紹介
片桐一男[カタギリカズオ]
1934年(昭和9年)、新潟県に生まれる。1967年、法政大学大学院人文科学研究科日本史学専攻博士課程単位取得。文学博士。現在、青山学院大学文学部名誉教授。公益財団法人東洋文庫研究員。青山学院大学客員研究員。洋学史研究会会長。専攻は蘭学史・洋学史・日蘭文化交渉史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
14
江戸時代166回に及んだ長崎オランダ商館長の江戸参府旅行のうち最後の1850年の旅行を、館長本人の日記及び日本側史料を突合しつつ分析した本。著者には阿蘭陀通詞や鷹見泉石、杉田玄白に関する著作があり、それらと重複する処は略されている。シーボルトの日本地図流出事件から時期的には離れておらず、流石に江戸においては厳しい日蘭交流制限が見られるが、既にやや緩んでいる。抑々緩い我が国情では厳しい統制が元々効かなかったようだ。又、既に5年の滞在経験のある商館長の記述からは異文化交流の驚きは伺えない所がやや残念ではある。2024/03/11
-

- 和書
- 上海キャンディ