- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
上念司[ジョウネンツカサ]
著・文・その他
内容説明
ビジネスモデルを変えた天下人・秀吉の国内&対外政策とは?朝鮮半島ではなく、マニラを攻撃していれば、世界地図は塗り替わっていた…!?足利家滅亡から本能寺の変、山崎の戦い、検地・刀狩、対キリシタン、朝鮮出兵まで、国防の本質を“経済的視点”で描く―。「織豊時代」を学べば、現代日本を救える!!
目次
信長と秀吉
第1部 「貨幣制度」が歴史を作る(「悪貨」が「良貨」を駆逐する?;東アジアの貿易メカニズム)
第2部 秀吉の国内政策(信長の遺志を受け継いだ秀吉;牙をぬかれた寺社勢力)
第3部 秀吉の対外政策(キリスト教国の脅威;「朝鮮出兵」失敗の本質)
著者等紹介
上念司[ジョウネンツカサ]
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
22
自ら発行できない明の銅銭から、銀山、金山の発展から銀、金の流通が拡大してくる。自ら鋳造して明の銅銭と交換できるようにした撰銭を持ってしても貨幣としての利便性を確保できなくなり、金、銀を中心に考えていた信長と違って秀吉は貨幣のような機能を備える米を軸に据える。しかし、米は社会が豊かになり、余るようになると価値を減じていく。2018/03/30
TheWho
13
経済の視点から歴史を再評価するシリーズ本。今回は、織田信長が、本能寺で憤死後安土期から桃山期である豊臣時代の実態を経済から論ずる。国内総生産が増加しながら明銭の枯渇でデフレ不況に陥っていた戦国末期、貨幣経済をすすめていた信長から石高制と銀の並立で、後の江戸時代における米本位制への先鞭をつける事になるが、秀吉は国内貨幣鋳造推進もやり近世金融政策を始める先見性もあった。しかし市場経済と国政の期待を見誤り秀吉死後の政権崩壊に繋がる。秀吉の足跡を視点を変え楽しめる1冊です。2020/06/10
Mark X Japan
6
経済的視点でのキリスト教・朝鮮出兵を教科書のよりも広い視野で捉えているので,視界が大きく開けました。後書きにもあるように,歴史の授業は何だったのでしょうか。マルクス史観や資料重視主義が原因なのでしょうか。数年後に始まる歴史総合の教科書は,本著のような内容になることを願っています。記念すべき2,200冊目が本著で良かったです。☆:4.52018/12/08
紗窓ともえ
6
冒頭は信長、そして秀吉と、シリーズの中では異色の普通のページ配分です。しかし、信長も秀吉も迫り来る帝国主義の脅威を既に見据えていたという教科書だけでなく過去の歴史書が触れてこなかった切り口です。その点は少し前に読んだ「超日本史」と共通する捉え方です。経済の切り口が歴史を専門にする人よりもスッキリ理解できてストンと納得。でも初めてだと分かりにくい?大東亜戦争→明治維新→信長と書かれた順に読む方が理解が深まります。2018/03/30
チョキ
5
基本的なスタンスは異なるが戦国時代の貨幣経済を通貨供給量から分析してるのは興味深い。2018/10/03
-
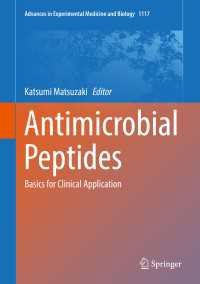
- 洋書電子書籍
- 松崎勝巳(京都大学)著/抗菌ペプチド:…
-

- 電子書籍
- オメガトライブキングダム(11) ビッ…







