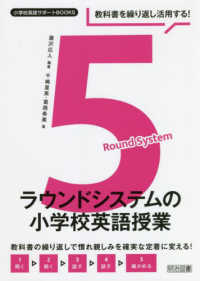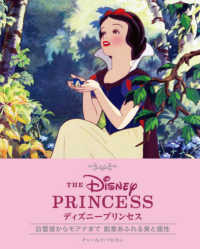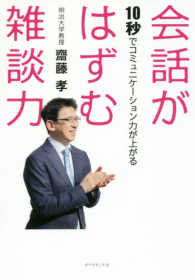出版社内容情報
日々を楽しく暮らすことを信条とした江戸っ子たち。落語のあらすじをベースに、彼らが好んだ四季のご馳走を、さまざまなうんちくを織り交ぜながら紹介する至極のエッセイ。
内容説明
江戸時代後期にはじまった落語では、「日々を楽しく暮らすこと」を信条とした江戸っ子の機転と人情が、旬の「ささやかなご馳走」とともに数多く描かれる。鰻屋とその隣人の勘定をめぐるおかしな掛け合い、貧乏な若夫婦の夕飯が芋のみなのが可哀想と、気前よく自分たちが食べる米の飯まであげてしまう噺…。春は筍、夏は鰻、秋は秋刀魚、冬はうどんにねぎま鍋。季節の食を楽しんだ江戸っ子の粋。
目次
第1章 新春―お正月を飾る庶民のご馳走
第2章 春―旬を食せば…
第3章 初夏―初物を食べる
第4章 夏―酒の肴の定番料理
第5章 秋―実りの秋とは言ったものだが…
第6章 冬―鍋にまつわる、あれやこれや
終章 江戸の食文化を知るその他の落語
著者等紹介
稲田和浩[イナダカズヒロ]
1960年東京都生まれ。大衆芸能脚本家、作家、ライター。日本脚本家連盟演芸部副部長、文京学院大学外国語学部非常勤講師(芸術学)。おもに落語、講談、浪曲などの脚本、喜劇の脚本、演出を手掛ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
65
落語とそれに関する食べ物をまとめた一冊。内容的には考証というよりエッセイ、紹介という体なんだけど、題材が題材なので読んでいると何処か駘蕩とした空気が漂ってくるような気がする。旬の物という言葉が死語になりつつある現代だけど、やはりそれぞれの時期に合った食べ物というのはあるものだなあ。あと紹介されている落語も多岐に渡り、「目黒のさんま」や「あたま山」「らくだ」とかの時分でも知っている名作から、聞いた事の無い物まで挙げられているが、どれも面白そうなのである。旨い物を食べながら酒が呑みたくなるような一冊でした。2020/05/03
絵
18
食べ物の登場する江戸落語が、季節に分けて全部で30以上紹介されています。江戸の庶民の生活もエッセイ風に描かれていて勉強になりました。 「日々を楽しく暮らすこと」を信条とした江戸っ子たちの、ささやかなご馳走がいいですね。 「うどん屋」「ねぎまの殿様」「二番煎じ」など、噺家さんたちが麺類や鍋物など温かいものを食べる仕草がいつも美味しそうだな〜と感じます。 2024/09/25
ようはん
12
古典落語から見た江戸の食文化史。落語はあまり知らなかったが、随所に紹介される数々の落語は割と面白かった。2020/02/04
まゆ
5
落語の脚本家が落語に登場する四季の食べ物を紹介してくれる。江戸落語というタイトルからあるように、古典落語中心だから、食べ物は江戸時代の風習の紹介とセットになりとても面白い。落語の紹介ももちろんあるので初心者も興味を持てて、落語が聴きたくなる本。2020/04/18
Inzaghico (Etsuko Oshita)
5
江戸落語版と上方落語版の両方で「青菜」を聴く機会があった。本書でとりあげられているのは「鯉のあらい」だが、そのお供の「やなぎかげ」というお酒が実においしそうなのだ。お金もちが飲むお酒という扱いで、植木屋さんがご相伴に与るという噺だ。「やなぎかげ」は江戸だと「なおし」。みりんとお酒で割った飲みものと知って驚いた。それだったら植木屋さんが毎日飲んでいる普通のお酒のほうがおいしそうに思えるのは、飲兵衛の性か。2019/12/02
-
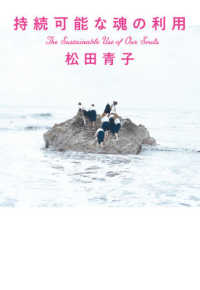
- 和書
- 持続可能な魂の利用