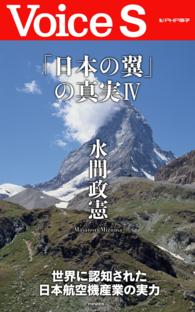出版社内容情報
日本人は心という摩訶不思議なものとどう向き合い、表現してきたのか? 江戸思想をベースに宗教や民間伝説など様々な角度から追う。
はじめに
一、 「こころ」の本源を探る
鏡──『荘子』/「至人」/道元/「古鏡」/盤珪/「不生の仏心」/鉄眼/「本心」/「三種の神器」/「心は神明の舎」/藤原惺窩/「格物」/「物欲を去る」/朱子学と陽明学/「怒りを遷さず」/「良知」
虚──熊沢蕃山/「太虚」/「活発流行」/「心中悪なきのみならず、善も又なし」/囚われない心/『論語』の「空」/幕末の陽明学
敬──神話/『古事記』/スサノヲの物語/スサノヲの多面性/中世のスサノヲ/朱子学の性善説/闇斎のスサノヲ論/素直さ/「心神」
理──「心ナリノ理」/「愛」/「忠」/「静坐」/「カノ一理」
二、心を養う
自由──芸道/『五輪書』/『兵法家伝書』/『天狗芸術論』/「煩悩即菩提」
安楽──石門心学/小天地としての人間/道話
歓喜──妙好人
三、「こころ」の不思議に向き合う
四端──伊藤仁斎/「卑近」/「活物」としての心/「徳」/「四端」の拡充/「寛宥の心」
礼楽──「古文辞」/「くるわ」/「君子」/庶民/徳川社会と人々の心
恋──本居宣長/「歌の本体」/恋の歌/「人情」/「物の哀」を知る/『源氏物語』/心の深層
悪──神とは何か/善と悪/死
むすび
あとがき
【著者紹介】
HASH(0x3df6418)
内容説明
江戸時代の思想といえば、封建的な道徳や無味乾燥の教学で埋め尽くされているだろうと思っていた方が、なかなか面白いではないか、今の自分たちと結局は同じ問題にぶつかっていたのだな、そんな風に読んでくだされば、この書物が世に出た意味があると私は思っている。こころを巡る葛藤でつながる江戸時代の人と私たち―。
目次
1 「こころ」の本源を探る(鏡;虚;敬;理)
2 「こころ」を養う(自由;安楽;歓喜)
3 「こころ」の不思議に向き合う(四端;礼楽;恋;悪)
著者等紹介
田尻祐一郎[タジリユウイチロウ]
1954年水戸市生まれ。東海大学教授。近世儒学、国学、神道などの日本思想史が専門(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Haruka Fukuhara
♨️
はちめ
Go Extreme
Asakura Arata