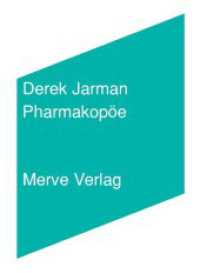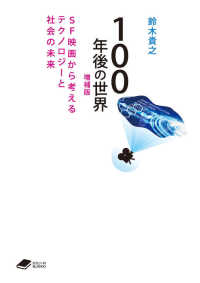内容説明
年頭、昭和天皇が崩御した。中国では民主化要求のデモを弾圧する「天安門事件」が起こった。中・東欧の共産圏ではソ連の軛が一挙に緩み、ドミノ式に政権が倒れた。さらに長く冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊した。これらの事件が連鎖しながら起きた一九八九年の歴史的意味を探る。
目次
第1章 昭和天皇のトラウマ
第2章 社会主義が目指したもの
第3章 冷戦の構図
第4章 〓(とう)小平、ゴルバチョフの登場
第5章 天安門事件―「改革開放」とブルジョア民主化の間
第6章 東欧の「逆ドミノ革命」
第7章 ソ連・東欧の軛はなぜ緩んだか
エピローグ―一九八九年以後のソ連
著者等紹介
竹内修司[タケウチシュウジ]
1936年生まれ。59年、東京外国語大学卒業後、文藝春秋に入社し、雑誌、書籍の編集に携わる。2000年、退社。文教大学情報学部教授を経て、現在はフリー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。