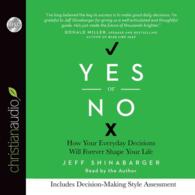内容説明
頭のかぶるものも、さすものも、どうして同じカサなのか、オモざし、カオだち、ツラがまえ、顔をいう言葉が三つあるのはどういうわけか、「信じる」と漢字の音から動詞を作る以前、カミとヒトとのかかわりはどんな言葉で語られたのか…、身近なことばの由来をさぐるとき、日本語を語ったむかしの人々の、姿と心が見えてくる。
目次
カサをサス―雨に歌えば、まずは祝言
男たちの名まえ―みやこの人々、おクニはどちら
オモざし・カオだち・ツラがまえ―列島の顔とりどり
ソヒ(添)とげる―爺婆の夢の果て
焼けノ・ハラ―田畑が火田だった頃
ウマい、シブい、ヱグい―草食・根食人の味覚
ネル(練)―手・足・心のスローな意義
オニごっこ―疎外・人食い・なり変わり
マにウケる―動詞「信」はどうよむか
ケハヒ(気配)とオト―人・物・神の「ケ」のはい方
トキの向こう―「時と永遠」への古代的観想
おナゴリ惜しい―船出を見送る、霊をながす
著者等紹介
木村紀子[キムラノリコ]
1943年生まれ。松山市出身。奈良大学名誉教授。専攻は言語文化論・意味論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
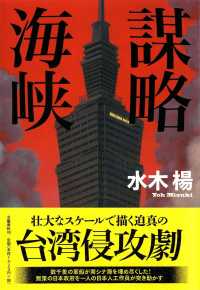
- 和書
- 謀略海峡