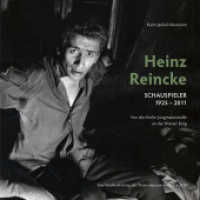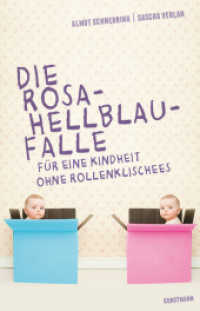出版社内容情報
ハングルは15世紀に、驚くほど精緻な「音の分析」をもとに創られた文字。現代の言語学者も驚嘆するその〈緻密な仕組み〉とは? 圧倒的な漢字文化の只中で、文字革命はいかに行われたのか?
内容説明
現代の言語学者も舌を巻くほどの精緻な「音の分析」によって、一五世紀の中頃、“ハングル=訓民正音”は創られた。圧倒的な漢字文化のまっただなか、合理的な仕組みと、美しさを兼ね備えた文字を、国王と若き学者たちは、どのように創ったのか?「音が文字になる」奇跡の瞬間を、ハングルの創生とともにたどる。
目次
序章 ハングルの素描
第1章 ハングルと言語をめぐって
第2章 “正音”誕生の磁場
第3章 “正音”の仕掛け
第4章 “正音”エクリチュール革命―ハングルの誕生
第5章 “正音”エクリチュールの創出
第6章 “正音”―ゲシュタルト(かたち)の変革
第7章 “正音”から“ハングル”へ
終章 普遍への契機としての“訓民正音”
著者等紹介
野間秀樹[ノマヒデキ]
1953年生まれ。朝鮮言語学、日韓対照言語学、韓国語教育を中心に、音論、語彙論、文法論や言語存在論などの論著がある。2005年大韓民国文化褒章受章。また、美術家としての活動もある。1996‐97年ソウル大学校韓国文化研究所特別研究員。前東京外国語大学大学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
松本直哉
35
エリートの使うラテン語から自由になるために俗語で書き始めたダンテが一市民だったのに対して、エリートの使う漢文から自由になるために声なき声の多数派のための文字の考案を命じたのが世宗という為政者である点が特異。音韻学の萌芽さえもなかった15世紀に、朝鮮語の音韻の成り立ちを精緻にしらべ、分子から原子のレベルまで明らかにして、それを忠実に形にしたハングルの構造がいかに先進的であったか、ハングルをようやく躓きながら読めるようになったばかりの私にはピンとこないところもあるが、新書なのに充実の内容と豊富な参考文献。2021/09/20
Shoji
31
ハングルが成立した意義を知りたくてこの本を読んでみた。 アジア各国は漢字文化であった。日本も韓国も漢字文化であった。 しかし、漢字だけでは限界があった。 簡単に言うと、貴族と庶民の差である。貴族は漢字を使えるが、庶民はそうでない。 そこから生またのが、仮名でありハングルである。 「ハングル」は「韓民族の文字であり、世界で最高の文字」という意味であり、ユーラシア東方の極に現れた奇跡である、と言われている。 確かにそう思った。 日本は、漢字、仮名、カナ全てが必要であるからして、、、、。うーん、難解だ。2016/05/04
ntahima
19
講演に備え、予習も兼ねて再読する。国や人と同じく本にも幸運な出会い、不幸な出会いがある。初めての海外に向かう機上で読んだケルアックの『路上』は生涯忘れ得ない一冊となった。韓国語に出会い、留学先の韓国で著者の講演を韓国語で聞けたのだから、この本との出会いは当然前者であろう。本の題名は『ハングルの誕生』であるが内容は韓国語についてだけではない。文字を創出する為には先ず言語とは何かを知る必要がある。ハングルの構造を概観しながら言語一般について改めて考えさせられた。韓国語が分らなくても充分に楽しめる筈。三読予定。2012/05/30
Porco
15
『ハングルの誕生』というタイトルですが、ハングル以前の漢字漢文の話や現在に至るまでの展開、さらには「形のない音声に文字という形を与えるとはどういうことか」という言語学の話まで盛りだくさん。お腹いっぱいになる力作です。2016/07/30
なつきネコ@着物ネコ
14
レポートのために足りないハングル知識を得ようと読んでみた。ハングルだけでなく言語学に片足を突っ込んでいる。半分も理解できたか怪しい。オノパトペが豊富な朝鮮には漢文では限界があった。故に民衆にはなじまない下地があった。文字を知らない民のため音を表す文字をつくる。まだ、当時は母音も子音の感覚もないなかで音を理解し分解し、簡単に表す。それをやり遂げたハングルの凄まじさ。最初のハングル解説本にある。「風声、鶴淚、鶏鳴、狗吠と云えど、皆得て書くべからん」の一文に漢文で表現できない鳴き声を表す文字の勝利を表している。2022/02/16