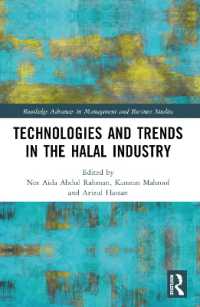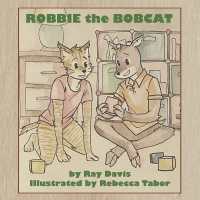内容説明
厳しい戒律があるにもかかわらず、いつしか日本仏教界にできあがっていた「男色」文化。稚児をめぐって争い、失っては悲しみにくれ、「持戒」を誓っては、何度も破る―。荒れはてた仏教界に、やがて「戒律復興」の声とともに新たな仏教を生みだす人々が現われる。戒と僧侶の身体論から見た苦悩と変革の日本仏教史。
目次
第1章 持戒をめざした古代(なぜ戒律が必要となったのか;待たれていた鑑真と国立戒壇;延暦寺戒壇の成立;戒をめぐる“現状”)
第2章 破戒と男色の中世(守れなかった戒―宗性の場合;僧侶の間に広がった男色)
第3章 破戒と持戒のはざまで(中世日本に興った“宗教改革”;女性と成仏;戒律の復興を人々に広める;延暦寺系の戒律復興と親鸞)
第4章 近世以後の戒律復興
著者等紹介
松尾剛次[マツオケンジ]
1954年長崎県生まれ。東京大学大学院博士課程を経て、山形大学人文学部教授、東京大学特任教授(2004年度)。日本中世史、宗教社会学専攻。1994年に東京大学文学部博士号を取得。日本仏教綜合研究学会前会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
獺祭魚の食客@鯨鯢
61
曹洞宗の開祖である道元が比叡山で修行して離脱したのは当時の僧侶たちの堕落ぶりに幻滅したからだそうです。 当時国家鎮護宗派として天台宗と眞言宗は絶大な権威を有していました。しかし釈迦が唱えた十の戒律を守ることなく女色、男色、乱暴狼藉等々とても聖職者とは思えない行動の数々。織田信長が焼き討ちをしたことを批判することはできません。 眞言宗では「理趣経」という性を肯定する経典があり、空海に最澄が教えを請うたが断られたという逸話もあります。灌頂や稚児などの同性愛は宗教世界では当たり前であったようです。 2020/07/19
モリータ
11
◆破戒=男色が中位以下の僧にまで文化として広まっていたことを東大寺の宗性の誓文で示したうえで、鎌倉期の持戒運動=国立戒壇を経ない(死穢等による行動制限のない)自戒による利他的な社会事業の実践を西大寺(真言律宗)の叡尊に焦点を当てて論じる。後者はちょうど奈良で真言律宗の寺をいくつか回っていたので勉強になった。◆親鸞の「無戒」がそれ以前の破戒状況へのもう一つの反応ということはありそうだが、記述の量が上記二部にくらべて少ないので何とも言えない。2019/03/05
海星梨
5
ちょっと物足りなさが。集中できてないからかな?紹介されてたエピソードは多くて、戒律から日本仏教史を捉え直すのにはいい本なのかも。2020/03/01
鈴木誠二
3
視点を変えた日本仏教史。様々なエピソードがめっちゃ面白い!「男でありながら、女の姿をし、夜には男色の相手をした童子であったと考えられます」(春日野権現記絵の解釈)。男の娘のルーツ?「子供の成人年齢は当時(13世紀頃)当時、普通15歳であり、童子たちも、15歳になれば大人となり、男色の受け手から、男色をする側へと成長を遂げていったのかもしれません。」これが受けから攻めのルーツ? など、事実はフィクションより先行していたのか? と、妄想の翼を広げるのも楽しい。2017/10/10
ひよピパパ
3
叡尊や忍性といった律僧にスポットをあてながら、日本仏教史上の戒律の様相について分かりやすく説明されている。時代順に説明がなされており、各時代の仏教界の様子も容易に見て取れたのでありがたかった。ただ、戒律についての説明は、もう少し整理して述べてほしかった。2015/04/08