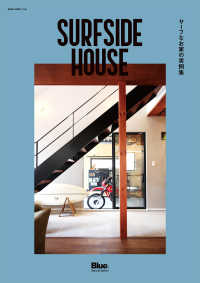出版社内容情報
厳しくもあたたかな幸田文の視線は、自身の、そして他人への老いにも向けられていた。いかに芯の通った老いかたをするか。人生の達人・文先生の生きかたから学ぶアンソロジー。
内容説明
人生の達人・幸田文の生きかたから、芯の通った老いかたを学ぶ随筆選。
目次
第1章 軽快な年寄りになりたい
第2章 上手に老いる知恵
第3章 老後の楽しみの見つけ方
第4章 年寄りのいる風景
第5章 祖母としての幸福
第6章 夫婦で老いるということ
第7章 老いとはこんなもの
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふう
66
作者が五、六十代に書いた老いに関する作品を、没後に孫が編んだ随筆集。身じたくとあるので、老いに向かうにあたっての心構えなのでしょうが、日々の暮らしの中で考えたことがさり気なく、でもしみじみと綴られています。いつも思うことですが、幸田氏の言葉や文は独特の味わいがあって美しく、伝えたいことがすっと胸にしみ込んできます。『老後の仕合わせとは、小さい仕合わせを次々と新しく積みかさねていくこと。仕合わせには永代続くものなどはない。』七十代のわたしも心の身じたくを意識し、小さな幸せを大切にしていこうと改めて思いました2024/05/29
ほう
33
幸田文さんの文章は、辞書を片手にじっくりと腰を据えて読むことが多い。私の知らない言葉がたくさん出てくるからなのだけれど、それ以上に美しい日本語に触れたくてページを捲る。文章の最後に年齢が記されているが、ここはとても考えさせられる。2022/07/19
くるみみ
15
随筆をテーマ毎に編集したシリーズの7冊目。お孫さんが編集に携わっている。あとがきによると『幸田文が自身の老いを身近に感じ、周囲からの老いの話を見聞きするうになった日々のことが綴られている』とあり、1編の最後に掲載年と当時の幸田氏の年齢が記されていることが読後に感慨深くなるし、参考になると思った。年金受給年齢が上がったことも1例に昔より「老人」とする年齢は上がっているけれども確実に身体も頭脳も若くはないわけだから自覚しつつ、振り返りながらも「老い」に静かに向き合っているような文章ばかりでとても良かった。2022/03/13
hitsuji023
5
あとがきで著者が老いというテーマに拒否反応を示した、とある。それを見つめる作業の辛さがわかっていたのだろう。しかし、読んでいる私たちには老いについて考え、参考になる一冊となった。2024/07/12
あきひと
5
幸田文さんの随筆全集の中から、「老い」にまつわる文をお孫さんがまとめたもの。ご自身の老いに対してジタバタしたところは全く感じられず、一歩引いて俯瞰しているように語っていて、清々しささえ感じる。 子どもの頃、親の実家のおばあちゃんの話が良い味出してたことを思い出した。2023/04/30
-
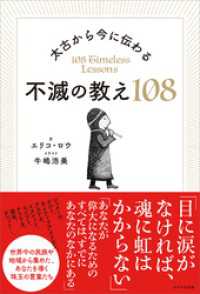
- 電子書籍
- 太古から今に伝わる 不滅の教え108