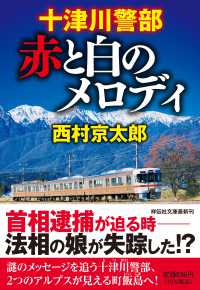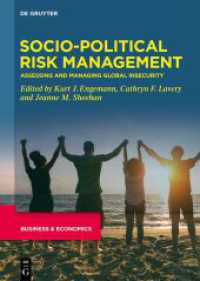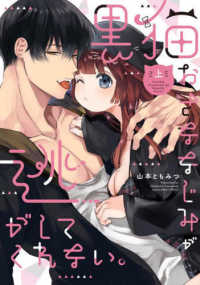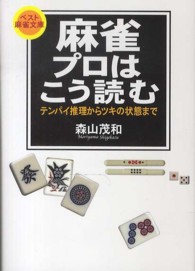出版社内容情報
製鉄の町・八幡を舞台にした著者初の自伝的小説。敗戦の年に生まれたヒナ子は複雑な家庭環境のなか、祖父母のもとでたくましく育つ。
内容説明
敗戦の年に生を享けたヒナ子は、複雑な家庭事情のなかで祖父母のもと、焼け跡に逞しく、土筆のように育ってゆく。炎々と天を焦がす製鉄の町・北九州八幡で繰り広げられる少女の物語。自伝的小説。
著者等紹介
村田喜代子[ムラタキヨコ]
1945年、福岡県八幡(北九州市)生まれ。87年「鍋の中」で芥川賞受賞。90年「白い山」で女流文学賞、97年『蟹女』で紫式部文学賞、98年『望潮』で川端康成文学賞、99年『龍秘御天歌』で芸術選奨文部大臣賞を受賞。2007年、紫綬褒章受章。10年『故郷のわが家』で野間文芸賞、13年『ゆうじょこう』で読売文学賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
87
昭和20年、終戦間近の北九州の八幡を舞台にした小説。日本製鐵八幡製鐵所があって、隣接した小倉市には陸軍造兵廠があった。広島から夫のある身の女を連れて駆け落ちした仕立て屋。こいつは、ほかの男のもっているものを欲しがる情炎の性癖がある。そんなことを繰り返す。最初の数頁に、広島を原爆の描写がある。加えて、八幡製鐵社長の三鬼隆が乗った日航機「もく星号」が伊豆大島三原山噴火口に墜落した話も出てきて、時代背景をしっかりととらえている。ピカドンの標的にされたが、長崎が犠牲になり難を逃れた戦後八幡の市井の人間模様。→2025/03/01
たま
69
戦後すぐの八幡の群像劇、村田喜代子さん自身が1945年八幡市生まれだそうで、子ども時代の貴重な記憶がつまっている。三姉妹とその夫(建具師、下宿屋、仕立て屋)の家庭が軸で、それぞれ女の子を育てているが、3家族とも実子ではない。戦争や病気で親を失くした子どもの多い時代、3人とも明るく元気なのがうれしい。風呂は銭湯に行ったり他所の家で貰い湯したり。私の場合村田さんより下の世代の核家族でこんな密な近所づきあいはなかったがそれでも懐かしく感じた。企業城下町ならではの八幡製鉄の存在感にも昭和を思い出す。2025/05/29
ゆみねこ
63
製鉄所の町八幡を舞台に、少女ヒナ子の成長を描く。村田さんご自身と同い歳の彼女がこれからどんな物語を紡いで行くのでしょうか?女たらしの仕立屋克美の生き様ももっと見てみたいですね。第一部了とあるので、続編がとても楽しみです。2015/08/01
なゆ
62
北九州といえば、八幡製鉄所。鉄を溶かす炎が常に燃え盛り、鉄があって人々の暮らしがある。そんな製鉄城下町八幡の街の人達の、戦後の活気と熱気と人情にあふれた作品である。原爆の話からはじまるのは、八幡も原爆と無縁ではないからか。八幡に暮らす三姉妹とそれぞれの家族を中心に描かれる。貰われっ子や預かった子などそれぞれに複雑ながらも特別な事ではないらしい。小学生のヒナ子の目に映る八幡の暮らしが生き生きと楽しくて、続編が楽しみで仕方がない。対称的に、テーラー瀬高の克美の冷めた目線と女にだらしないダメぶりも気にかかる。2015/06/14
そうたそ
40
★★★★☆ 製鉄所のある町八幡を舞台に少女ヒナ子がたくましく育つ姿を描く自伝的小説。ヒナ子に著者自身の姿を重ねて描かれているであろうことは伺えるし、何よりヒナ子が主人公であるのだが、それ以上に印象深いのが仕立屋の克美。製鉄業で賑わう町の勢いが製鉄所で燃え盛る炎と重なり、更にはヒナ子が生き生きとして育つ様もそれと相俟って印象深く描かれるのだが、随所に登場する克美のいかにも女たらしな様とその描写は作中でも目に見えて浮くほど艶かしくそして気味悪い。第一部完とあるので続編もあるのだろう。今から楽しみだ。2015/06/23