出版社内容情報
『マヌ法典』は、B.C.2世紀からA.D.2世紀にかけて成立した代表的なインド古典法。ヒンドゥー教の教義の支柱として、今日までインド社会の社会文化規範の基底を成す。
内容説明
『マヌ法典』は世界創造から社会と人生の理法を説き、インド社会の原型を規定したヒンドゥー教の古代法典であり、インド古典文学の至宝でもある。サンスクリット原典からの全訳。
著者等紹介
渡瀬信之[ワタセノブユキ]
1941(昭和16)年、秋田県に生まれる。1968年、京都大学大学院文学研究科梵語梵文学博士課程中退。東海大学名誉教授。専攻、インド古代文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
紀元前200年-紀元200年頃に成立し、ヒンドゥー教の規範とされる本書がカースト、不浄観、輪廻的宇宙観を仏教と共有するのは、先史時代からのインドの習俗が組み込まれたからだという。一方、両者が異なるのは禁欲主義についてである。個人の欲望を抑えるために出家する仏教に対し、本書は社会規範を逸脱しない善悪の規定によって欲望を制御する。創造と破壊を繰り返す宇宙と神に定められたカーストから成る男性中心のヒンドゥー社会は、詳細な法規範(ダルマ)によってヴェーダを教えるバラモンとそれを学ぶ王権以下の3階級に組織化される。2026/01/07
isao_key
5
マヌ法典-ダルマシャスートラは、紀元前6世紀頃、それまでの家中心の正統的な社会が揺らぎ、再編が求められていた中、ブラーフマナ、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラの4つの身分体制の確立とそれぞれの行為規範の策定を目的として編纂されたという。この後19世紀半ばまで、ダルマシャーストラはその使命を果たし続けることとなった。日本語で法典と訳され、法律書と誤解されるようになったが、その本質は幼児期から老年年期までの人として生涯いかにあるべきかを事細かく確定することにあり法律、司法に相当する部分は一部分でしかない。2014/11/17
うちこ
1
輪廻思想がベースにあり、来世のために罪を「償う」のではなく「除去」しようとするインド。この概念がないと、あんなに浄化オタクみたいなヨーガはしない(笑)。すてきな再刊です。 【巻末 東洋文庫での再刊にあたって より】⇒再刊に際しては、訳文および訳注の一部改訂を行なったが、最も重要な点は、ヴェーダ=ダルマの世界における重要観念の一つである罪の清めに関して、これまで一般的に用いられてきた「贖罪」という訳語を改め、「罪の除去」としたことである。すなわち「罪を償う」という観念は存在しないからである。2014/11/20
-

- DVD
- 子供たちは見ている
-
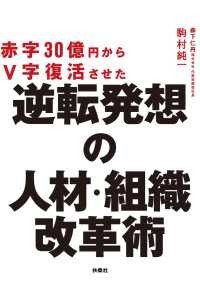
- 電子書籍
- 赤字30億円からV字復活させた 逆転発…






