感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ryoichi Ito
5
ケンペル(1651-1716)はドイツの医者,博物学者。出島の三学者の一人。1690-1692年滞日。その間1691年,1692年の2回,商館長の江戸参府に従った。本書はその時の日記。日本事情を詳細に記した「日本誌」の一部。江戸旅行は往復3ヶ月ほど,百人余の人数だった。江戸では将軍綱吉に拝謁した。好奇心旺盛な綱吉は様々のことを質問し,ケンペルは将軍の前で踊ったり歌ったりさせられた。ケンペルはその著書「廻国奇観」で日本の植物を多数紹介,リンネはその記述に基づきイチョウ,ツバキなどに学名を与えている。 2023/07/20
あや
2
綱吉の時代、長崎に滞在していた東インド会社の船医ケンペルの、二度に渡る幕府推参の日記。こういう肩書きだとどうということなく感じてしまうが、解説によると、様々な国を渡り歩き無数の要人の信頼を得た博物学の天才であった。そんな彼でも日本においては「蘭人」の1人としてみなされ、見参の際に婦女子の見せ物になったり、歌やダンスや日常会話の再現を求められている。当時を生きた外国人の目線で改めて綴られる江戸の記録はリアルかつ新鮮で、いくつかの聞き間違い・認識違いも面白かった。2023/09/21
isao_key
1
本書はドイツの啓蒙思想家ドーム編によるケンペル『日本誌』第2巻第5章の部分に他の章を加えたものある。なので本文を読むと始まりと終わりの前後の脈絡がよく分からない。『日本誌』は幕末に日本を訪れた外国人に読まれた本でペリーの本にもよく出てきた。ケンペルは1690年オランダ商館付の医師として出島に約2年滞在したのち、1691年と92年に江戸参府をして徳川綱吉と謁見している。この2年の日本国内旅行記が本書に詳しく記されている。日本全般にわたる事柄について書かれた初めての記録であり、江戸城内の様子まで述べている。2014/04/24
アライニコ
0
将軍綱吉の時代に長崎の商館で医者してたオランダ人の、江戸に将軍に謁見するためにした旅行の記録。当たり前に通り道に刑場があって、伊勢参りの道中の庶民が乞食ってて、「オランダ人と話すと汚れるから寄るな」と庶民を自分たちから遠ざけようとする役人にイラッとしたり、その他細かくいろんな事物を記録している2012/04/02
6ちゃん
0
江戸初期に日本にやってきた医師の旅行記。とにかく外国人ではしゃぐ日本人が笑える。また、あまりの貧しさに泣く。江戸時代に対する憧憬のようなものが合っているところもあるけど、五人組のような監視社会の暗さも見えてくる。江戸時代が好きな人はクリアした方がよい本だと思う。
-

- 電子書籍
- 異世界チートサバイバル飯【分冊版】 4…
-
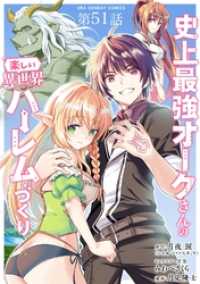
- 電子書籍
- 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレ…







