出版社内容情報
近世の日本では、古学をはじめとした儒学のほか、蘭学や国学などのさまざまな学問が生まれ、多くの個性豊かな思想家たちが誕生してきた。朱子学を支配的な思想とするかつての「常識」を否定し、「武威の国」日本の支配思想を兵学であるととらえ、その対立軸としての朱子学との関係を基本としながら、経済の発展とともに登場する蘭学・国学との関わりを説く。著者の近世日本思想史研究を決定づける一冊。
【目次】
序章 近世日本思想史の四本軸
一 内発的な「日本人」意識
二 「武威」の国家
三 近世国家のなかの朱子学
四 兵営国家の支柱としての兵学
五 蘭学・国学発生の社会的背景
六 蘭学者の「国益」意識
七 国学者の「皇国」意識
八 近代日本のナショナル・アイデンティティ
1 兵学
第一章 兵学と士道論――兵営国家の思想
一 兵営国家と兵学
二 兵学の国家統治論
三 山鹿素行の兵学
四 山鹿素行の士道論
五 幕末の兵学
付論1 中国明代の兵家思想と近世日本
2 朱子学
第二章 「武国」日本と儒学――朱子学の可能性
一 「孔孟の道」と国家
二 華夷観念と「武国」
三 「武国」日本の朱子学の可能性
四 儒教文化圏のなかの近代日本
付論1古賀?庵の海防論――朱子学が担う開明性
付論2女性解放のための朱子学――古賀?庵の思想
3 蘭学
第三章 功名心と「国益」――平賀源内を中心に
一 「国益」論者平賀源内
二 「芸」による功名
三 源内の「日本人」意識
四 蘭学者の「国益」意識
五 源内と宣長
4 国学
第四章 近世天皇権威の浮上
一 「下から」の天皇権威
二 第一期 儒仏論争と神国論
三 第二期(一) 増穂残口の「日本人」意識
四 第二期(二) 垂加神道の救済論
五 第三期(一) 本居宣長の天皇観
六 第三期(二) 平田派国学の天皇観
七 明治国家の一君万民論
付論1 太平のうつらうつらに苛立つ者――増穂残口の思想とその時代
付論2 本居宣長の「漢意」批判
付論3 大嘗祭のゆくえ――意味付けの変遷と近世思想史
あとがき
平凡社ライブラリー版?あとがき
解説――前田史観へのいざない 先崎彰容
内容説明
近世の日本では、古学をはじめとした儒学のほか、蘭学や国学などのさまざまな学問が生まれ、多くの個性豊かな思想家たちが誕生してきた。朱子学を支配的な思想とするかつての「常識」を否定し、「武威の国」日本の支配思想を兵学であるととらえ、その対立軸としての朱子学との関係を基本としながら、経済の発展とともに登場する蘭学・国学との関わりを説く。著者の近世日本思想史研究を決定づける一冊。
目次
近世日本思想史の四本軸
1 兵学(兵学と士道論―兵営国家の思想)
2 朱子学(「武国」日本と儒学―朱子学の可能性)
3 蘭学(功名心と「国益」―平賀源内を中心に)
4 国学(近世天皇権威の浮上)
著者等紹介
前田勉[マエダツトム]
1956年、埼玉県生まれ。東北大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。愛知教育大学名誉教授。博士(文学)。専攻、日本思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
zunzun
Go Extreme
マウンテンゴリラ
-
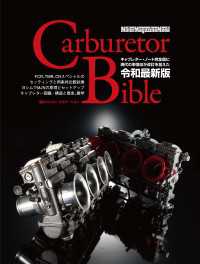
- 電子書籍
- Carburetor Bible
-
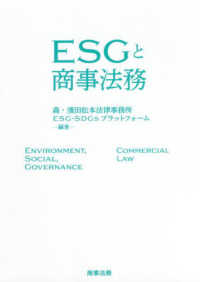
- 和書
- ESGと商事法務
-

- 電子書籍
- 【無料試し読み版】門外不出の最強ルーン…
-

- 電子書籍
- 午後の磔刑 王国記Ⅵ 文春文庫
-
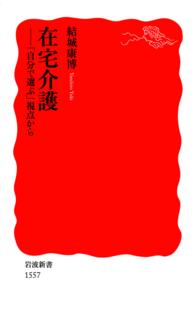
- 電子書籍
- 在宅介護 - 「自分で選ぶ」視点から …




