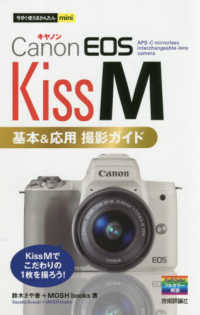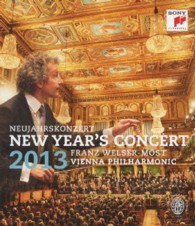内容説明
横尾忠則は三〇代の時、総持寺、永平寺、青苔寺などの禅寺に毎月通っていた。数回の坐禅、掃除などの作務、食事、就寝など、朝から晩まで修行をしている。いったい何のために?そこで何かをつかんだのか?そして悩みの種を“安楽死”させることはできたのか?スティーブ・ジョブズの禅体験が話題になっている今、坐禅を知るための待望の一冊。
目次
1 参禅の旅(禅に魅せられて―総持寺参禅;自分自身をよく知る―竜泉寺参禅;全てを捨てさる―永平寺別院参禅 ほか)
2 日常・自然としての坐禅(自分の脚下をみる;自然に身を任せる;旅に自然に孤り行く ほか)
3 坐禅で何を感じたのか(参禅記;禅体験;輪廻転生を考える ほか)
著者等紹介
横尾忠則[ヨコオタダノリ]
1936年、兵庫県西脇市生まれ。美術家。1972年ニューヨーク近代美術館で個展。その後、パリ、ベネチア、サンパウロのビエンナーレに招待出品。2006年のパリのカルティエ現代美術財団での個展開催など、海外での作品発表も多い。小説『ぶるうらんど』で泉鏡花文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
SOHSA
26
《図書館本》タイトルに惹かれ手にとった一冊。あの横尾忠則が禅に傾倒していたとは知らなかった。作者の実体験を綴った坐禅修行記は単純に読み物として面白い。なかなか一般人には馴染みの薄い参禅体験は、そうであるからこそ、読み手の目を惹くことばかり。むしろそれだけで良かった感も。終盤の輪廻転生や心の安楽死は、作者独自の宗教観ではあるけれど、敢えてそこは語らずにいて欲しかった。ともあれ坐禅はやはり深い。老師の言葉は容易には体現できない。そう言えば40年程前に訪れた鹿野山禅林の坐禅体験をふと思い出した。2021/09/16
黒猫
20
なんと40年前に書かれた本。坐禅を組むために各地のお寺を巡り、老師と対談する。正直に自分の考えをぶつけて、悟るとは何か?無とは何か?仏教とは何か?何のために座るか?これらのことを実際にお寺に参禅しながら体験していく。その意味では宗教書というより、体験談として面白い。今でこそ禅はブームだが40年前にどれだけの人がやっていたのか?著者は永平寺の厳しさに辟易した模様(笑)その辺りも素直に書いてあり面白い。2018/10/07
どらがあんこ
12
修行記というタイトルであるが著者が本書のあとがきで述べているように禅寺に遊びに行っているようで楽しそうである。生まれながらにして悟っているという言葉が出てくるが、座禅という行為はその状態から階段を下ろすように自分という存在を見つめ直す行いなのだろうか。言葉や思想を忌避するわけではなく、悟りの状態から再構成するのである。座禅というと静かなイメージがあるが実はそのような動きを生み出すための一行程なのかもしれない。2021/03/10
geromichi
5
夜な夜なこの本を読みながら瞑想したものです。秋の夜長にどうぞ。2019/02/05
さっちも
5
芸術家だから感覚的に禅を捉えるのかなぁと思ったが、すごい合理な人。文章も明晰で読みやすいし分かったふりしないから共感できる。座禅をはじめたら陥るあるあるや、面白さに共感しっぱなしだった。禅をしたい、しているのだが、本で語られるあまりにも遠くの景色に気後れしたり、感情移入できない人。読んで見る価値あると思います。禅に全く知識のない人は分かりにくいかも。2016/09/24