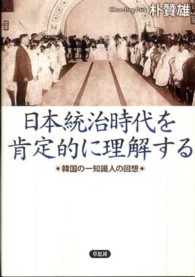内容説明
川とは、人にとってどのような存在なのか。近代治水技術の発展と限界を歴史的・具体的に検証し、自然との共生をめざす治水のあり方、「溢れても安全な治水」とは何かを追究した画期的著作。脱ダム問題なども含め、近年の研究を踏まえた新論考「川の本質を考える」を増補した新版。
目次
第1章 近代治水の勝利と破綻(水防と治水;近代治水の功罪)
第2章 川の個性と水害(地質と河川の特徴;沖積平野を流れる河川の三形態;川を変える自然の猛威;川の流れと降雨;人の営みと水害の変化)
第3章 自然の制約と技術の限界下で―近世の川と水害(北上川の大改修と舟運体系;桂離宮にみる水害への対応;『百姓伝記』にみる水防・治水思想;利根川の舟運・治水体系と浅間山の噴火;信濃川・阿賀野川の分離と近世技術の限界)
第4章 近代技術の登場と水害への対応の変化(信濃川大河津分水;終わりなき利根川治水;ダムによる洪水の調節;治水計画と排水ポンプ;弱体化した水防)
第5章 自然と共存する水害への対応(総合治水対策;超過洪水対策;水害対応策のあるべき姿)
著者等紹介
大熊孝[オオクマタカシ]
1942年8月、台北市生まれ。引き揚げ後、高松、千葉、長岡、新潟に住む。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博士。新潟大学自然科学系工学部建設学科教授。専門は河川工学、土木史。自然と人間の関係がどうあればいいのかを、川を通して研究しており、川の自然環境を守るとともに、治水・利水のあり方を地域住民の立場を尊重しながら考察している。NPO法人新潟水辺の会代表、通船川・栗ノ木川下流再生市民会議会長、水郷水都全国会議共同代表ほかを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Book & Travel
山口透析鉄
ぼっこれあんにゃ
とりもり
soto