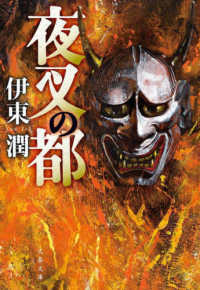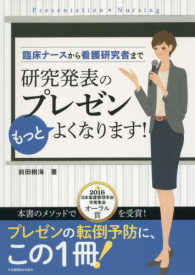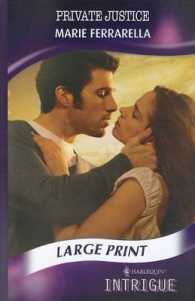出版社内容情報
広範な庶民の子女が寺子屋に通いはじめてから近代小学教育が確立するまで、「いろは」が文字教育の中心だった百年を、外国人の日本語学、印刷技術などの視角も含め描き出す。
内容説明
十九世紀がはじまる頃、寺子屋は盛んになり、ひろく庶民の子弟が読み書きの習得に励むようになる。この世紀の終わりに、小学校教育が制度化され、五十音図に切り替わるまで、文字学習の出発点は「いろは」。「いろは」の世紀に、文字教育はどのように営まれたか。外国人の東洋語理解や出版の変化も絡めながら多角的に描き出す言語・教育文化史。
目次
1 「いろは」とはどういうものか
2 寺子屋の「いろは」(入門としての「いろは」;往来物で学ぶ;寺子屋から学問・芸道の世界へ)
3 西洋人の「いろは」(ロニー―仮名活字の製作者;ヘボン―日本宣教と辞書;チェンバレン―日本学の大成者)
4 小学校の文字学習(「いろは」から「五十音図」へ;小学校で漢字を学ぶ;近代的な小学校へ;木版本から活字本へ―文字の統一)
5 「いろは」の十九世紀
著者等紹介
岡田一祐[オカダカズヒロ]
1987年生まれ、千葉県出身。北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現在、北海学園大学人文学部講師。専攻、平仮名を中心とする日本語文字・表記史の研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
軍縮地球市民shinshin
5
う~ん、結局何が言いたいのかイマイチよく分からなかった。2024/04/27
kozawa
3
「いろは」(雑に言えばひらがな)を中心に、庶民への読み書きが明治に学校教育へ継承されつつ組み替えられていく歴史を興味深く辿っている。 全体的に簡易で読みやすいのだが、それでも読んでいて「どういうこと?」って気になったことはググると、「そうなんだ」って発見があったりして、短いページの中で語られる内容は実は濃密。軽く流し読んでもよし、じっくり精読してもよし。 本書の内容をより深く興味がある向きは巻末の書籍紹介がある。何より本著者の本格的なものが先に出ている。2022/08/10
Go Extreme
1
「いろは」とはどういうものか 寺子屋の「いろは」: 入門としての「いろは」 往来物で学ぶ 寺子屋から学問・芸道の世界へ 西洋人の「いろは」: ロニー―仮名活字の製作者 ヘボン―日本宣教と辞書 チェンバレン―日本学の大成者 小学校の文字学習: 「いろは」から「五十音図」へ 小学校で漢字を学ぶ 近代的な小学校へ 木版本から活字本へ―文字の統一 「いろは」の十九世紀2022/05/10