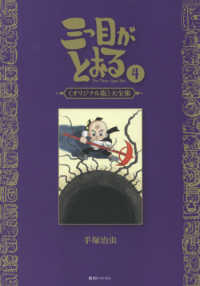出版社内容情報
死体の変容をつぶさに追う観想の文学『九相詩』、骸骨が生き、愛し、死ぬ物語『一休骸骨』に、この国の死生観をみる。
今西 祐一郎[イマニシ ユウイチロウ]
国文学研究資料館館長
内容説明
日本の物語は、歌は、死をどのように描いたか。『源氏物語』が初めて人の死をくわしく語ったあと、中世には、屍の変容を凝視する『九相詩』が、近世には、骸骨たちが睦みあい、病み、死に、葬られる、ユーモラスな版本『一休骸骨』が知られる。そこに生きているのは、日本人のどんな死生観であるのか。
目次
1 死を語る(『源氏物語』の死;蝉の殻)
2 醜悪な死(『今昔物語集』;不浄観;谷崎潤一郎が描く不浄観)
3 『九相詩』(腐敗する屍;『九相詩』の盛行;『九相詩』とキリシタン;キリシタン版『倭漢朗詠集』;版本『九相詩』にない歌;奈良絵風『九相詩』;「生前相」のある『九相詩』)
4 『一休骸骨』(宴に興じる骸骨;死ぬ骸骨;『一休骸骨』の成立)
5 『九相詩』と『一休骸骨』の合体(『九相詩』の利用;現代の『一休骸骨』)
著者等紹介
今西祐一郎[イマニシユウイチロウ]
1946年、奈良県生まれ。京都大学文学部卒業。現在、国文学研究資料館館長。専攻、日本古典文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のむ
4
『源氏物語』『一休骸骨』など、日本の出版物における死の表現。この本では、死の表現からみえる死生観という思想面はあまり掘り下げない。そこが少々物足りなくもあったが、シリーズのコンセプトが「書物をひらく」であるブックレットなので、致し方なし。個人事だが本文中に出てくる谷崎潤一郎『少将滋幹の母』をつい最近よそでも見かけて気になっていた。思わぬ邂逅に驚くとともに、下賤な言い方になるが思い切りネタバレを踏んだ気分。いや文学でネタバレは気にしないんだけど。2017/09/20
よの字
1
「死」について宗教的あるいは思想的に探求さる書ではなく、あくまでも出版物における「死」を紹介する一冊。なお、このシリーズは国文学資料館が平成26年より取り組んでいる、インターネットを通じて古典籍を一般に公開する「日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画(歴史的典籍NW事業)」の一環である、とのこと。2017/01/11
NyanNyanShinji
0
本朝メメントモリの「九相図」と「一休骸骨」。実際に墓を掘り起こして人の遺骸が朽ちてゆく様子を見る事で発心すると言う九想観。それでは物騒だからと絵に描いて代用したのが九相図。一方、擬人化された骸骨が笛や太鼓を鳴らしたり踊ったり、骸骨同士でキスをしたり,病気で死んだ骸骨を悼んで骸骨が剃髪して出家したり。人は所詮肉の衣を着た骸骨だと言わんばかりの一休骸骨。この二作は時には一つの作品に融合したりとバリエーションは豊かだったらしい。本書はふんだんにこれらの絵図を示してくれて眺めるだけでも楽しかった。2023/10/31