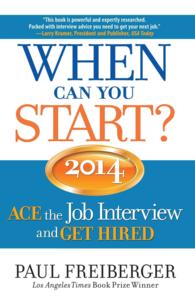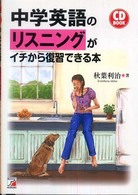出版社内容情報
漱石亡きあと、遺された夏目家の人々はどう生きたのか――。
日本近代文学の巨人・夏目漱石の孫にして、作家・半藤一利の妻でもある著者が綴る、個性豊かな親族たちとのエピソード。
当時を生きた著者だけが知る、夏目家に関するエッセイを集めた、滋味あふれる一冊。
「漱石の顔が千円札に登場した時、『お祖父さんがお札になるってどんなお気持?』とよく訊かれた。母筆子は、『へーえ、お祖父ちゃまがお札にねぇ。お金に縁のあった人とは思えないけど』という感想を述べたが、私にはこれといった感慨は湧かなかった。漱石にお祖父さんという特別な親しみを抱いたことがなかったからかもしれない。それは一つには四十九歳で没したため、私が漱石に抱かれたりした記憶を持たないせいであろう。しかし一番の理由は母が折に触れて語ってくれた漱石の思い出が、余りにも惨憺たるものだったからであると思う」――本書「母のこと・祖母のこと」より。
内容説明
祖父・漱石のこと、残された夏目家の人々のその後―個性豊かな親族たちとのエピソードを漱石の孫にして、半藤一利の妻が綴った滋味あふれるエッセイ集。
目次
第1部 ああ漱石山房(まぼろしの漱石文学館;漱石記念館への道)
第2部 祖母・鏡子の「それから」の人生(漱石夫人は占い好き;中根家の四姉妹;漱石夫人と猫;祖母鏡子と私)
第3部 松岡譲・筆子 父母の春秋(父・松岡譲のこと;祖母夏目鏡子と父松岡譲 ほか)
第4部 夏目家をめぐる小事件(漱石の長襦袢;難行苦行の十七文字 ほか)
著者等紹介
半藤末利子[ハンドウマリコ]
エッセイスト。1935(昭和10)年、作家の松岡譲と夏目漱石の長女筆子の四女として東京に生まれる。1944(昭和19)年、父の故郷である新潟県長岡市に疎開、高校卒業まで暮らした。早稲田大学芸術科、上智大学比較文化科卒業。夫は昭和史研究家の半藤一利。六十の手習いで文章を書きはじめる。夏目漱石生誕150年の2017(平成29)年、新宿区立漱石山房記念館名誉館長に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いつでも母さん
クプクプ
kawa
チョビ
ユジン姫
-

- 電子書籍
- 会社の問題の9割は「4つの武器」で解決…