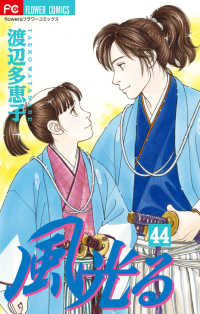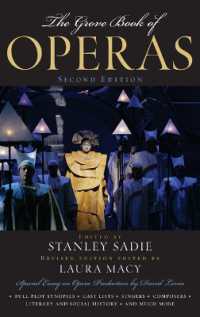出版社内容情報
2020年からのコロナ禍によって、都市部でも地方でも、鉄道の通勤・通学需要や観光需要が激減し、鉄道会社の経営は大打撃を受けた。
コロナ禍が終息しても、少子高齢化が続く限り、通勤・通学需要は減る一方だ。すでにローカル線の経営状況はかなり厳しく、バスへの転換も進んでいる。
しかし、バスへの転換は、交通弱者の外出の機会を減らしたり、自家用車の利用を増やして環境への負荷が増えたりするなど、デメリットも多い。
一方、成田・羽田・関空といった国際空港へのアクセス線の新設や西九州新幹線の開業、北海道新幹線や北陸新幹線の延伸、リニア中央新幹線の建設をはじめ、路線の新設・延伸の計画も数多くある。
ローカル線はどうすれば維持できるのか? あらたな路線は日本経済の起爆剤となるのか? また、鉄道を活用したあらたなビジネスに、各社はどのように取り組んでいるのか? さまざまな視点から考える。
内容説明
コロナ禍によって、都市部でも地方でも、鉄道の旅客は激減。鉄道会社は大打撃を受けた。コロナ禍が終息しても、少子高齢化が続く限り、通勤・通学需要は減る一方だ。すでにローカル線の経営状況はかなり厳しく、バスへの転換も進んでいる。しかし、国際空港へのアクセス線や新幹線をはじめ、路線の新設・延伸の計画も多くあり、新たな収益源を求める動きもある。鉄道会社が進むべき道とは?
目次
第1章 地方鉄道が生き残る道はどこにあるのか
第2章 新型コロナの衝撃を乗り越えろ!
第3章 コロナ禍前から将来へと続くトレンド
第4章 ヨーロッパで起こった鉄道事業の新自由主義化
第5章 規制緩和の波が日本へ
第6章 これからの鉄道網―経済の起爆剤になるか
第7章 鉄道をめぐるあらたな政策課題
第8章 日本の鉄道会社を支える「小林一三モデル」
著者等紹介
佐藤信之[サトウノブユキ]
1956年、東京都生まれ。亜細亜大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得。専攻は交通政策論、工業経済論。亜細亜大学講師、一般社団法人交通環境整備ネットワーク相談役、公益事業学会、日本交通学会会員。Yahoo!ニュース公式コメンテーター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
きみたけ
おいしゃん
あきあかね
Francis